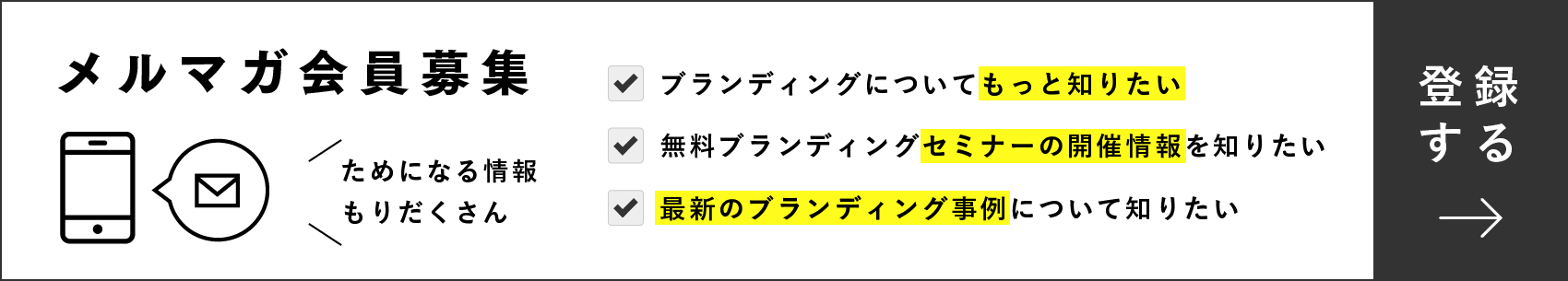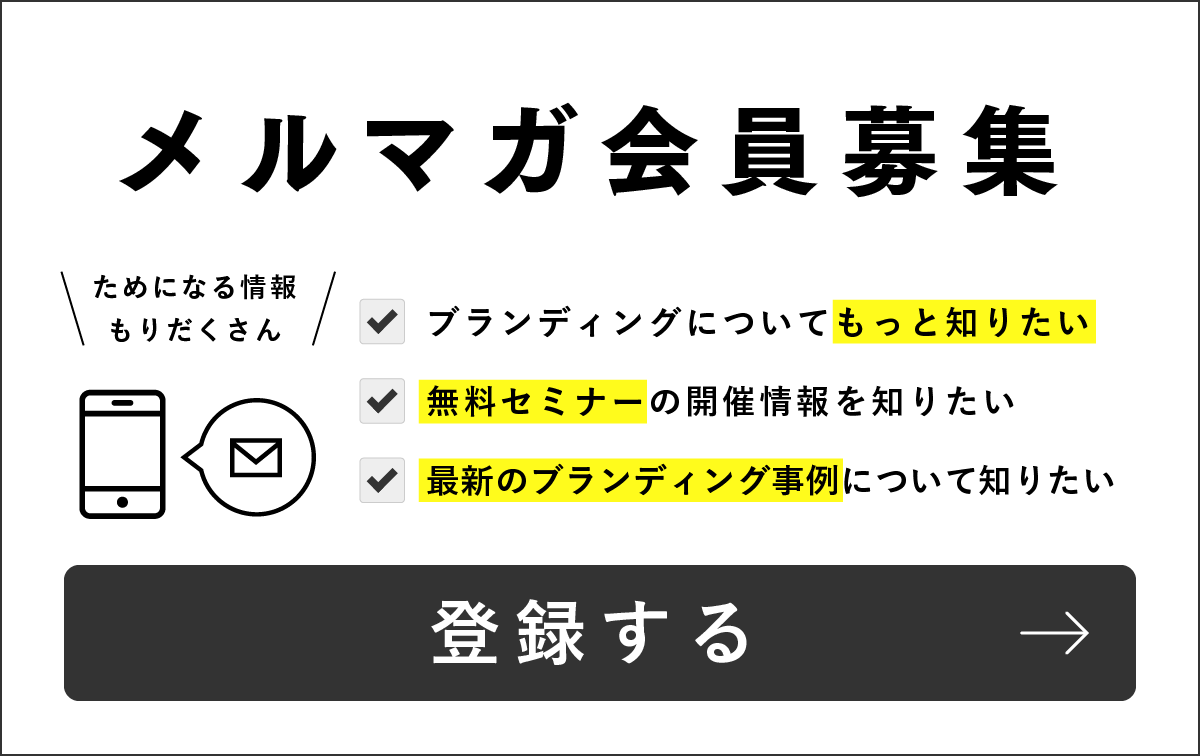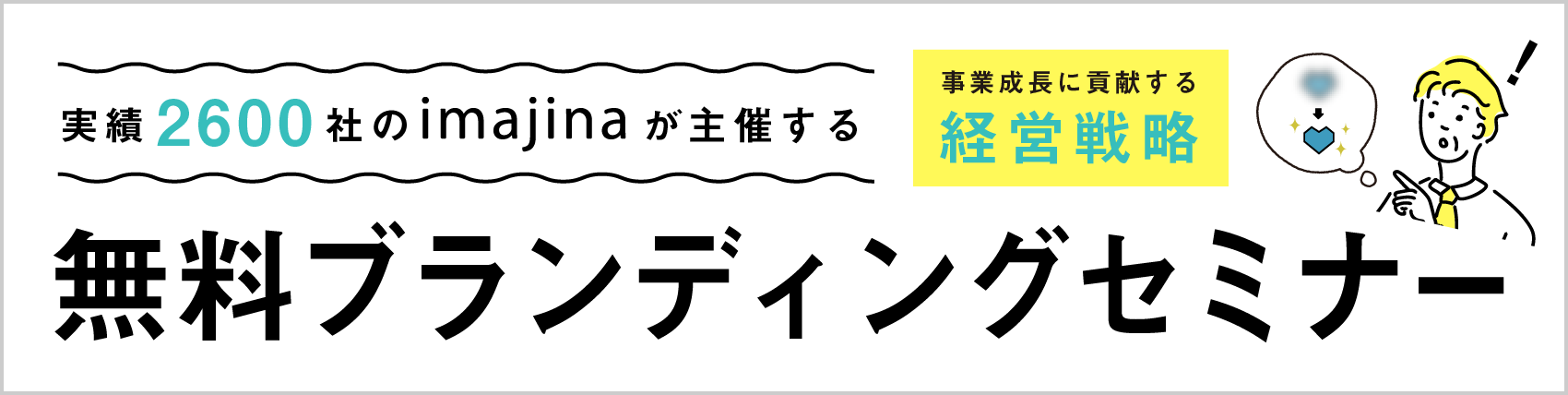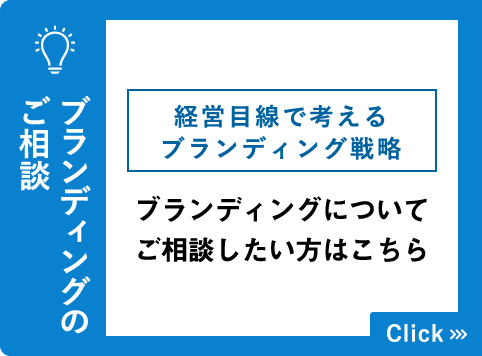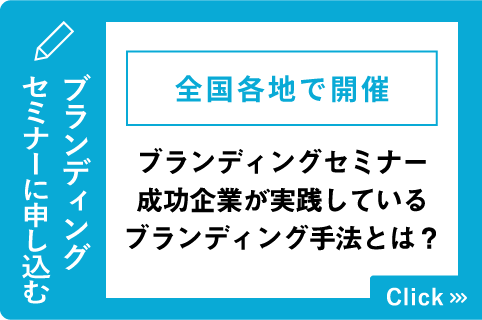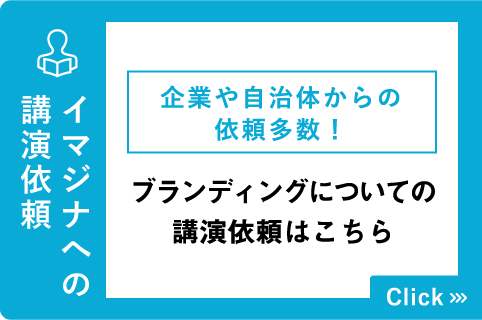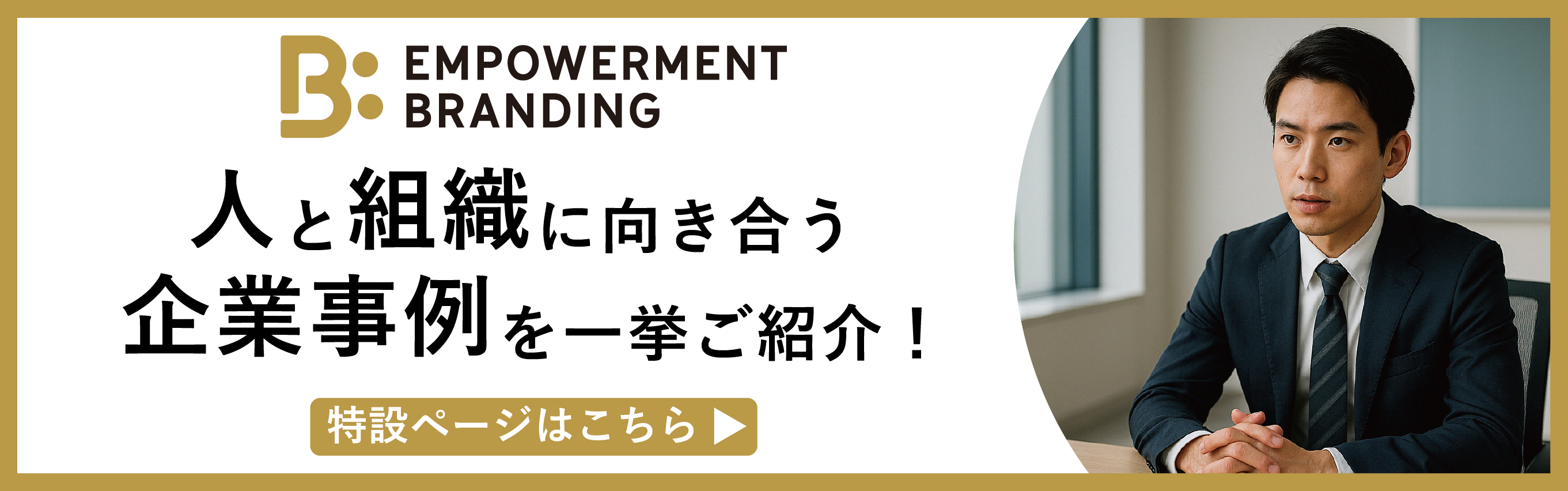INDEX [非表示]

新型コロナウイルスは、感染拡大から3年以上緊急事態宣言・まん延防止等重点措置は繰り返し発動されてきました。
人々の過度な往来を制限するための、大型商業施設の休業要請等の新たな措置なども設けられています。
商業施設や飲食店などにはしばしば「時短営業」や「営業自粛」が求められ、苦境にあえぐ経営者も多かったのではないでしょうか。
しかし、そのような状況下においても、リブランディングの実施に伴い、売り上げの維持・向上や立て直しが成功していた事例は少なからず見受けられます。
この記事では、リブランディングの重要性と実施する際のポイント、成功したビジネスモデルなどを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
リブランディングとは?
リブランディングとは、既存ブランドイメージの見直しを行い、方向性を調整・修正することでブランド力の向上を目指し、顧客への訴求力をアップさせる経営戦略のことです。
企業が確固たるブランドを築き上げてきても、時代の流れや世情の変化により、商品が社会のトレンドや顧客ニーズと乖離してしまうケースは珍しくありません。そこで、現状の問題点を洗い出した後、現在の顧客が持つ価値観やニーズに合うよう改善し、再構築する作業が必要となります。
リブランディングを行うことにより、既存ブランドが確立した知名度や人気は担保しつつ、新たな顧客の掘り起こしや販路拡大が狙えるでしょう。
ブランディングとリブランディングの違い
ブランディングとリブランディングでは、「ゼロからブランドイメージを作り上げていく戦略」か「既存のブランドイメージを変更する戦略」かという点が異なります。
ブランディングとは、自社ブランドに対する価値や権利を顧客と共有し、競合他社との差別化を目指す戦略です。
一方、リブランディングは、一度ブランドが成立してから、同じブランドを再度ブランディングし直す戦略を意味します。
リブランディングは、あくまでも既存のブランドを再構築する場合に使用される言葉です。
まったく別のブランドへ変更する場合は、リブランディングではなくブランディングと呼ぶべきでしょう。
リブランディングで問われる、インナーブランディングの重要性
長い歴史があるブランドほど、ブランドに対する共通のイメージが既に世に浸透している場合が多いでしょう。
では、そのような企業がなお、リブランディングに踏み出す理由はどこにあるのでしょうか。
ブランドによってさまざまなリブランディングの目的が挙げられますが、共通して「さらなる期待を醸成すること」や「より多くのファン(顧客)を獲得すること」が挙げられます。
目的を達成するために重要なことは「相手に魅力的だと思ってもらうこと」です。
ただ一方的に発信するだけでなく、相手に魅力的だと思わせるための施策に力を入れる必要があります。
企業はどんなタイミングでリブランディングを実施すべき?
企業がリブランディングを実施すべき主なタイミングは、下記の通りとなります。
- ブランドの表現・内容が時代に合っていないとき
- 自社のブランド同士が競合しているとき
- 顧客のターゲット層が変化したとき
- 新たな方向性を打ち出したいとき
- ブランドの成長が伸び悩んだとき
- 想定通りの効果・反応が得られないとき
- 好ましくないブランドイメージが浸透してしまったとき
- 事業継承が行われるとき
リブランディングは、ブランドの価値や受け継いできたものを最大限維持しながら、現在から未来の顧客にとって魅力的なものへ変遷させる作業になります。
特に事業継承が行われるタイミングなどは、よいところを残しつつ新しいものを取り入れるリブランディングに絶好の機会といえます。
リブランディングを実施すべきタイミングの中でも重要な4つのタイミングについて、以下にて解説します。
将来の方向性を定めたいとき
将来の方向性を定めたいときは、リブランディングのタイミングといえるでしょう。ブランドの顧客層が変化する時期があるためです。
それを予測し適切なタイミングで将来の方向を定めるのは重要かつ必要なブランディング戦略です。
企業はリブランディングで方向を定め、顧客層の変化に対応しなければなりません。
新しい市場に参入するとき
ブランドが新しい市場に参入するときは、これまでのブランディングではユーザーや顧客を獲得できない場合が多いです。
ブランドの既存イメージを損なわずに、新たなターゲットに向けてのリブランディングが重要となります。
市場の環境が変わったとき
市場の環境やニーズが変わったとき、リブランディングが必要になります。
市場の環境は時代とともに変化するため、それに対応したブランドに変えていく必要があるのは当然といえるでしょう。
これまでに培ってきた商品・サービスのスキルやノウハウは、企業にとって非常に価値のある資産です。
同時に、どれほど素晴らしいブランドでも、時代に即していなければ顧客から支持されることは難しくなります。
ブランディングが行き詰まっているとき
業績の伸び悩みや落ち込みはブランディングの行き詰まりが原因の場合があります。どんなによいブランドでも行き詰まるときもあるでしょう。
顧客やユーザーの気持ちが離れているならリブランディングすべきタイミングです。
リブランディングの手順は?
リブランディングには綿密な計画と実行が必要です。今がリブランディングのタイミングだと思っても計画なしに突き進めるのはおすすめできません。
以下で失敗しないリブランディングの手順を解説します。リブランディングする際の参考にしてください。
現状を分析する
リブランディングで重要なのはブランドの現状分析です。
不正確な分析を元に戦略を立てると的外れなマーケティングになってしまい、リブランディングに失敗する可能性が高くなります。
現状のブランドに好感を持っている顧客やユーザーもいるはずです。
リブランディングで新規顧客・ユーザーを獲得できたとしても彼らを逃してしまったらそれは成功したとはいえないでしょう。
彼らの心を掴み続けながらも、新しいニーズに対応するにはどうすべきかを分析・検討する必要があります。
戦略を策定する
現状分析の次は新しいブランド戦略の策定です。
「既存の商品やサービスで時代・時節に適応した好感度アップを狙うのか」または「新商品・新サービスなどで新たな顧客層を開拓するのか」などの戦略を立てましょう。
このときに重要になるのが、前ステップでの現状分析の結果です。「どの層をターゲットとするのか」「取り込める層はどの層なのか」を見誤ると戦略自体が不適切となります。
新ブランドを浸透させていく
新ブランドの浸透にあたり、戦略がブレてはなりません。
社員全員に新ブランドの必要性とよさを十分に理解してもらった上で、愛着をもって顧客やユーザーにアピールしてもらう必要があります。
新ブランドの浸透には広告やキャンペーンも重要です。想いを込めたメッセージや伝わりやすいキャッチコピーでターゲット層にアピールしましょう。
ブランディングについて知りたい方は、ブランドマーケッター育成講座に参加してみるのがおすすめです。
リブランディングで成功するためのポイント
リブランディングとは、即効性や永久性が期待できる戦略ではありません。
あくまでもブランドの価値を恒久的に維持・向上させる目的で行うステップの1つであり、状況や環境の変化に合わせて何度でも実施すべき施策です。
リブランディングでは長期的な目線と思考を持つとともに、いくつかのポイントを押さえることも重要です。
以下では、リブランディングを行う際の主なポイントを、5つ解説します。
現時点でのポジショニングを調査する
リブランディングを行う際には、現在自社のブランドがどのような状況にあるかを理解しなければなりません。
下記は、ブランドのポジショニングを調査する際にチェック・分析すべき項目の一例です。
- ブランドの資産価値
- ブランドの認知度
- ブランドの満足度
- ブランドに対する不満点
- 自社内で認識するブランドイメージ
- 顧客側が認識するブランドイメージ
- 市場・世間における自社ブランドの想起率
- 競合ブランドのポジション
現時点における自社のポジショニングを明確にすることで、今後「どのポジションを狙うか」「どのようなブランドイメージを作るべきか」を検討しやすくなるでしょう。
企業の核となる部分は変えない
リブランディングにおいて見直しや再構築の対象となるのは「企業の核となる部分をどのようにして世に認知させていくか」という「手段」の部分です。
企業の格となる部分とは、企業の経営理念や目的として掲げられる部分であり、ミッションやビジョン・ブランドコンセプトなどと呼ばれます。
例えば、老舗の和菓子店がパッケージをリニューアルしたり喫茶店を始めたりしても「おいしい和菓子を提供してお客様を喜ばせたい」という核心部分は変わりません。
企業の経営理念や目的を実現し、「より多くの人へ認知され支持されるには何をどのようにすればよいのか」それを見つめ直す作業がリブランディングです。
将来の投資という考えを持つ
リブランディングにかかるコストを「短期的に見て出費と捉えるか」「長期的に見て投資と捉えるか」で、企業の取り組み方や得られる結果には大きな差が生じます。
リブランディングを長期的な視野で捉える場合、下記の費用対効果が挙げられるでしょう。
- 自社ブランドの現状や課題を具体的に把握できる
- 既存顧客へブランドの魅力を再認識してもらえる
- 新規顧客へブランドをアピールできる
- 魅力あるブランドとして、将来的にも事業を継続できる
もちろん、すべてのリブランディングが確実に成功するわけではありません。
しかし、時流に合わせた変化と進化を怠らないことで、よりよい結果を生み出す可能性が高まります。
社内の理解を得る
リブランディングを行う際、社内の理解を得ることが大切です。
これまで浸透させてきたブランドイメージから脱却し、新しいブランドイメージを浸透させるには、新ブランドイメージを理解し共感してもらうための取り組みが必要となります。
しかし「うちの新ブランドイメージはこうだ」といきなり外向け(顧客向け)の発信をするのは危険です。
実態を伴っていなければ、いくら発信しても浸透せず、共感は生まれません。まず取り組むべきことは、自社の社員やスタッフに対する施策です。
個々の社員に、新ブランドに込められた想いや社会提供価値を浸透させ、さらに日々の業務に反映させて初めてブランドイメージは実態を伴ったものとして外部に伝わります。
ただ、これは容易なことではありません。社員をそういう気持ちにさせるには、一人ひとりに、それを自分事だと思う必要があるためです。つまり、ブランドイメージに込められた想いを実現することは、会社の将来性を広げるだけでなく、自分の成長にも繋がるのだという実感が必要になります。
『ブランドは社員から生まれる』
これは世界共通であり、時代が変化しようと普遍的です。
ブランドに込められた想いがすべての社員に浸透し、さらに、契約社員・派遣社員・アルバイト・パートに至るまで、想いを共有している必要があります。
定期的に成果を確認する
リブランディングを成功に導くためには、企業の経営層がリーダーシップを発揮し、戦略の舵取りを行わなければなりません。
リブランディングの実施とともに、経営層が明確な意思を表明・宣言した上で、定期的に進捗状況をチェックし軌道修正する必要があります。
企業の末端メンバーに至るまで、多くの人の意見や提案を募ることも、視野を広げる意味で有効な方法です。
しかし、企業のあるべき姿を長期的かつ俯瞰的に見て、最終的に判断し決定を下すのは経営層の仕事であり、自分たちが負うべき責任であることを忘れないようにしましょう。
リブランディングの成功事例
「ブランドの想いは一度伝えればよい」というものではなく、常に浸透し続け一人ひとりが共感しそれを広める“連鎖”を生み出すことが必要です。
以下に紹介するサーティワンのように、社員への想いの浸透施策(インナーブランディング)に力を入れることは、企業のリブランディングに大きな効果をもたらすでしょう。
以下、サーティワンをはじめとする成功事例を紹介します。
サーティワン
サーティワンは今年の4月1日にロゴの刷新を発表した。
リブランディングでは、ロゴやパッケージ・店舗の内装にまで一貫した想いを表現しています。
「『アイスクリームを売っているお店』から、『アイスクリームを通じて、もっと幸せをお届けするお店』を目指す」という想いのもと行われました。
サーティワンのブランディングに対する取り組みは、今回のロゴなどの刷新が始まりではありません。
根幹となるインナーブランディングがしっかり行われているからこそ、ロゴや内装のリニューアルに価値が生まれます。
サーティワンでは「『お客様をHAPPYにする』気持ちを1つにしよう」という想いを社員全員に浸透させるための社内コミュニケーションが充実しています。
代表的なものが、e-ラーニングシステムを活用した新人研修プログラムです。
さらに、知識や接客技術を披露し合う年に一度の「エクセレントスタッフチャレンジ」や、店舗全体で取り組む「31-PRIDE」といった各コンテストの開催・工場研修などがあります。
新しく加わるメンバーのみならず、既存のメンバーへも自社ブランドの想いを伝える取り組みがなされている点が特徴です。
スターバックス
「スタバ」の愛称で知られるスターバックスのブランド戦略は明確です。
自分たちが提供しているのは「コーヒー」ではなく「『サードプレイス』という空間を提供している」という意思を、社員からバイトに至るまで徹底的に教育し浸透させています。
仕事でマネジメントするのではなく文化でマネジメントすることで一人ひとりが裁量を持った行動が可能です。
その結果、お客様に合わせた柔軟な接客が可能となり満足度が高くなるでしょう。
スターバックスは、コーヒーショップとしては後発でありながら、ブランディングに成功し顧客を掴んだ成功事例です。
ニベア
「お子様からお年寄りまですべての方が使えるスキンクリーム」として1968年に売り出したニベアのスキンクリームは、鮮やかな青のパッケージとともに誰もが知っているクリームです。
子どもの頃から親しんでいるニベアは、自分が将来家庭をもったときにも子どもに塗ってあげようと思わせる効果が期待できます。
幼い頃から慣れ親しんだニベアのイメージは大人になっても忘れません。これがニベアの壮大なブランディングです。
湖池屋
ポテトチップスで有名な湖池屋もリブランディングに成功しています。ポテトチップスの値下げ競争から脱却し、付加価値の高い商品の主力化に成功しました。
「湖池屋のポテトチップスは料理人が作る」をモットーに、スローガン化してパッケージも変更しています。
「少し値段が高めでも美味しいものを」という市場のニーズに応えた見事なリブランディングです。
セブン-イレブン
コンビニといえば「近くて便利」で「スーパーより商品が高めでも売れる」という時代は終わりました。
それにいち早く気付いたのがセブン-イレブンを展開するセブン&アイです。
「近くて便利」はそのままに、ブランドに「美味しさ」「安全性」といった付加価値を付けました。
「ご家庭の味をお求めになりやすい価格で手軽に」も大きく前面に打ち出しています。
このリブランディングが功を奏し、従来の若い世代に加えてシニア世代の顧客を掴みました。まさに少子高齢化時代に適合した戦略といえるでしょう。
ブランドマーケティングについて詳しく知りたい方は、ブランドマーケッター育成講座へ参加してみるのがおすすめです。
リブランディングの成功事例から戦略を学ぶ
リブランディング成功のヒントとして、Appleとマクドナルドの事例を紹介します。
■Appleの事例 Appleは、あらゆる面で徹底したブランドの確立にこだわっています。例えば、シンプルかつデザインに優れ、統一性のある製品を作ることです。 Apple製品を一目見れば、多くの人が「これはAppleだ」と認識するでしょう。
同時に、Apple製品のユーザーにスマートで洗練されたイメージを持たせることで、ブランドへも上質な高級品としてのイメージを確立させています。
また、操作性を共通させ、Apple製品を使いこなすと他機種の操作もスムーズに行えることで「すべてをAppleでそろえる」という熱狂的なファンも獲得しました。
参考:Apple
■マクドナルドの事例 何年か前までであれば「マクドナルドとは?」聞かれたとき、安さや手軽さを挙げる人が多かったでしょう。 どちらかといえば子ども向け・学生向けの印象が強く「時間やお金のある大人が好んで入る場所ではない」というイメージを持つ人も少なくなかったです。
しかし、大人向けの商品開発や、知名度が高く大人に支持されるタレントをCMに起用し「大人が気軽に食べられる」というイメージを作ることに成功しています。
参考:マクドナルド
リブランディングについてもっと知りたい方は
サーティワンのように、ロゴの刷新といったリブランディングに取り組む企業は数多く存在しています。
しかし、ロゴの刷新など外部に発信されるデザインイメージの変更はあくまでも“手段”の1つであって、目的ではありません。
より多くの人にそのブランドに対する共通のイメージを抱いてもらうことこそが、重要となります。
そして、そのために最も有効な手段は、一人ひとりのスタッフに新たなブランドイメージを日々のサービスで体現させることです。
そういった根幹がしっかりしているからこそ、新しいロゴやデザインイメージも実態をもったものとして共感を呼び、広く認知されるに至ります。
弊社では「ブランドは社員からつくられる」という考えのもとインナー・アウターの両面へのブランディングを手がけています。
『社員も顧客も魅力的に感じるブランドづくり』について学べる無料ブランディングセミナーを対面とオンラインで定期的に開催しているため、ぜひお越しください。