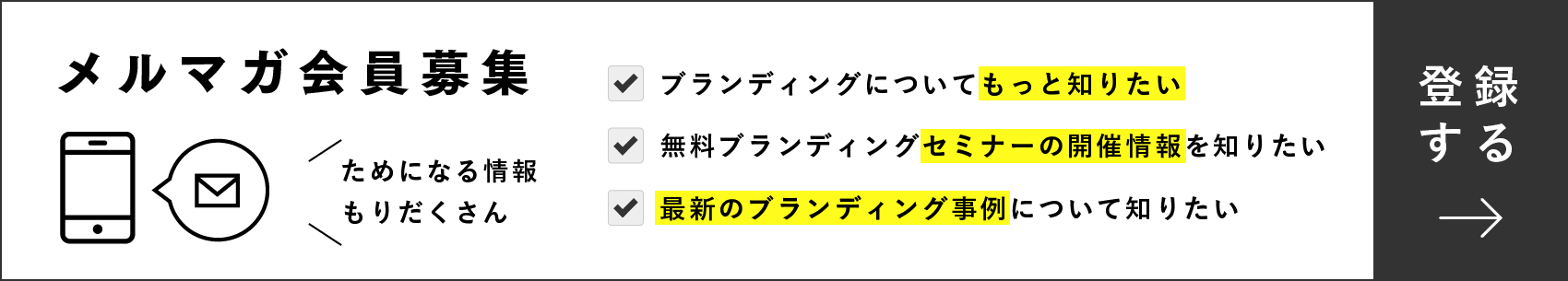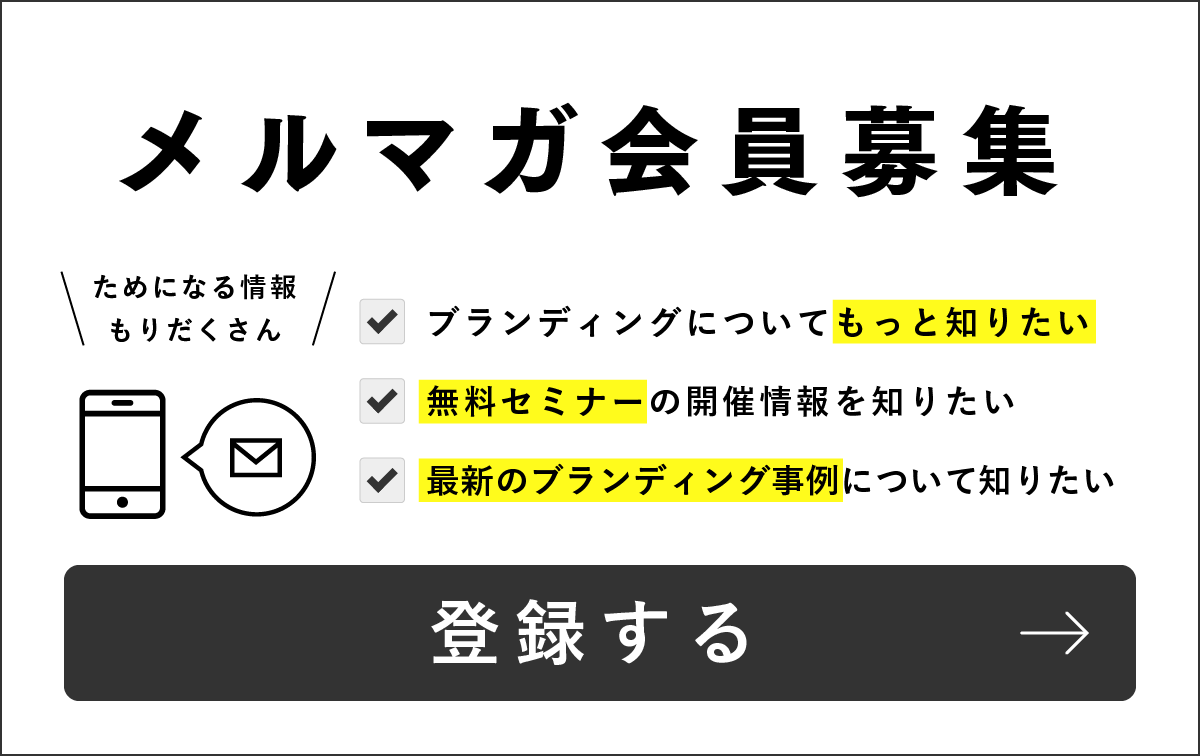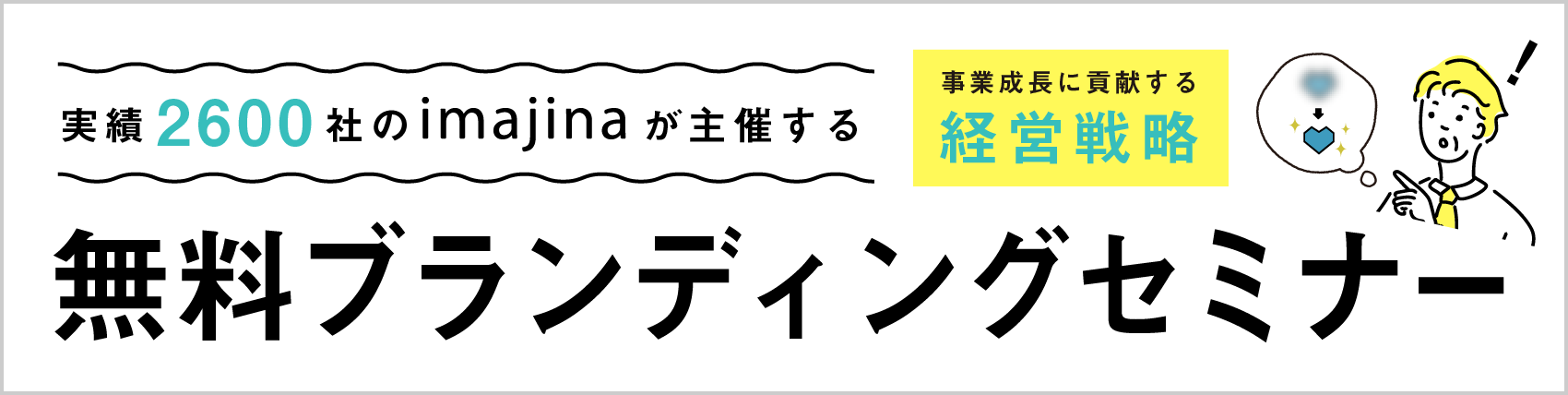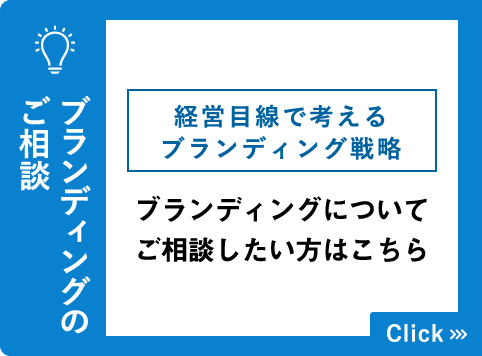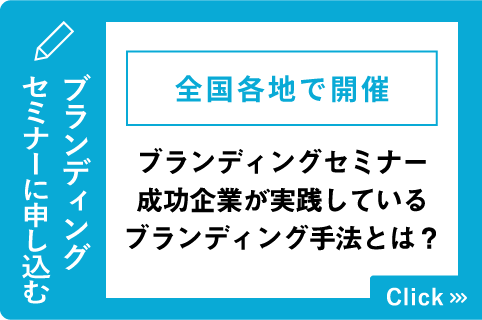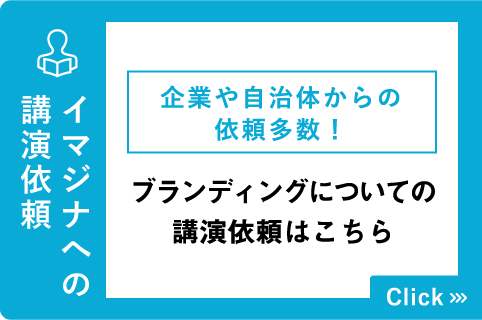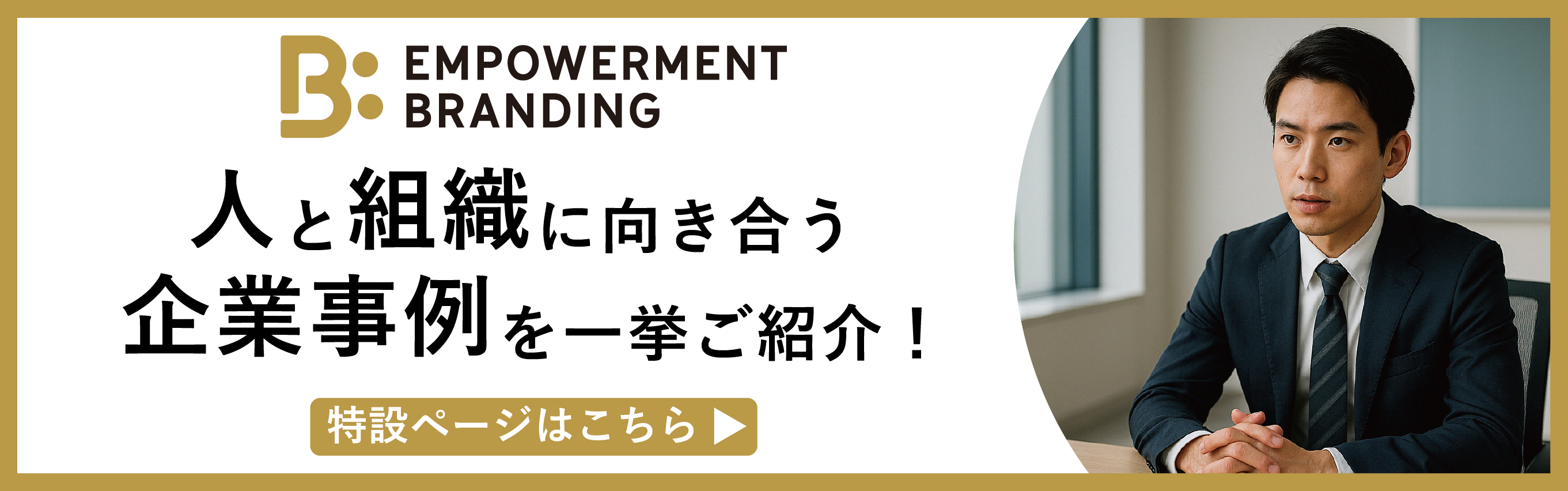すべてのビジネスの土台である「報連相」。
昨日は特に「報告」の重要性について紐解きましたが、今日は「連絡」について見ていきたいと思います!
そもそも、皆さん「報告」と「連絡」との違いを言語化できますか?
きっと、新卒や若手に「報連相は基本だ!」と日々伝えていらっしゃる方も多いかと思いますが、改めてそれぞれの定義を説明してほしいと言われれば少しドキッとするのではないでしょうか。
「報告」と「連絡」との違いについては様々な定義が存在しますが、ここでは
・報告=主に指示を出した相手に対し、次の意思決定や判断を仰ぐために情報を伝えること
・連絡=関わる人全員が意思疎通して業務を進めやすくなるように情報を伝達すること
としたいと思います。
連絡は、社内外で協働している人々と認識を揃え、業務を円滑に進めていくために必要不可欠ですが、どうしてもおろそかになりがちなポイントでもあります。
部下に対して、「もっとこまめに連絡すればいいのに…」「連絡が遅い!」と課題を感じられている皆様も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、データの力を借りましょう。
連絡を怠るとどんなまずいことがあるのか?そのような根拠から連絡の重要性を伝えることで、部下の行動も変わるかもしれません。
数字でみる、「連絡」が組織に及ぼす影響
■400万円
これは、コミュニケーション障壁が原因となって1年間に生み出されている、従業員1人あたりの生産性損失額です。
必要な情報が必要な相手へ伝達されていなかったために、余計な業務に手を付ける人が出たり、逆に重要な業務が後回しにされてしまったりという状況は、多くの組織に見られるのではないでしょうか。
こうした損失に一人400万円払うなら、その分給与を上げたいものです。
■5.7兆円
また別の、米国と英国の従業員10万人の企業を対象に行われた調査ではこれほどの大きな数字も出ています。
なんとこれは、従業員の“誤解”(会社の方針、ビジネスプロセス、職務など)から生まれる推定総コストだそうです。
人はそれぞれが異なるバイアスをもって生きているため、同じ情報を受け取っていても少なからず誤解が生じてしまいます。誤解をもった社員が、それを行動に移したり、別の社員に伝えたりすれば、組織全体における認識のズレもだんだんと広がっていきます。
結果、組織が一つの方向に向かって進むことができず、トータルでこんなにも大きな損失につながっているのです。
■5倍
最後に、ポジティブなデータにも目を向けましょう!
マッキンゼーの調査では、職場においてより詳細なコミュニケーションに参加していると感じている従業員は、そうでない社員と比べ、生産性の向上を報告する可能性が5倍高いとされています。
こまめに情報のやりとりをし、会社が向いている方向性や各業務の目的・プロセスなどを都度すり合わせることによって、仕事は圧倒的にスムーズになるのです。
皆さんに連絡を苦手とする部下がいらっしゃる場合は、上記のような根拠をぜひご活用ください!
「そもそもなぜ若手との間で意識のズレが生じてしまうのか」
「上司として、企業として、そこにどう向き合っていくべきなのか」
そんな、今知っておくべき社会の現状やマネジメントの考え方については、経営・ブランディングセミナーにてお伝えしています。