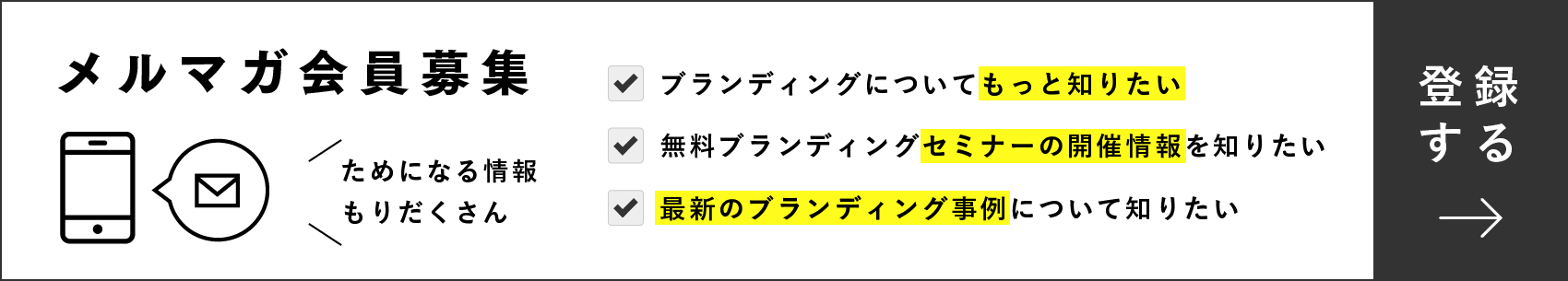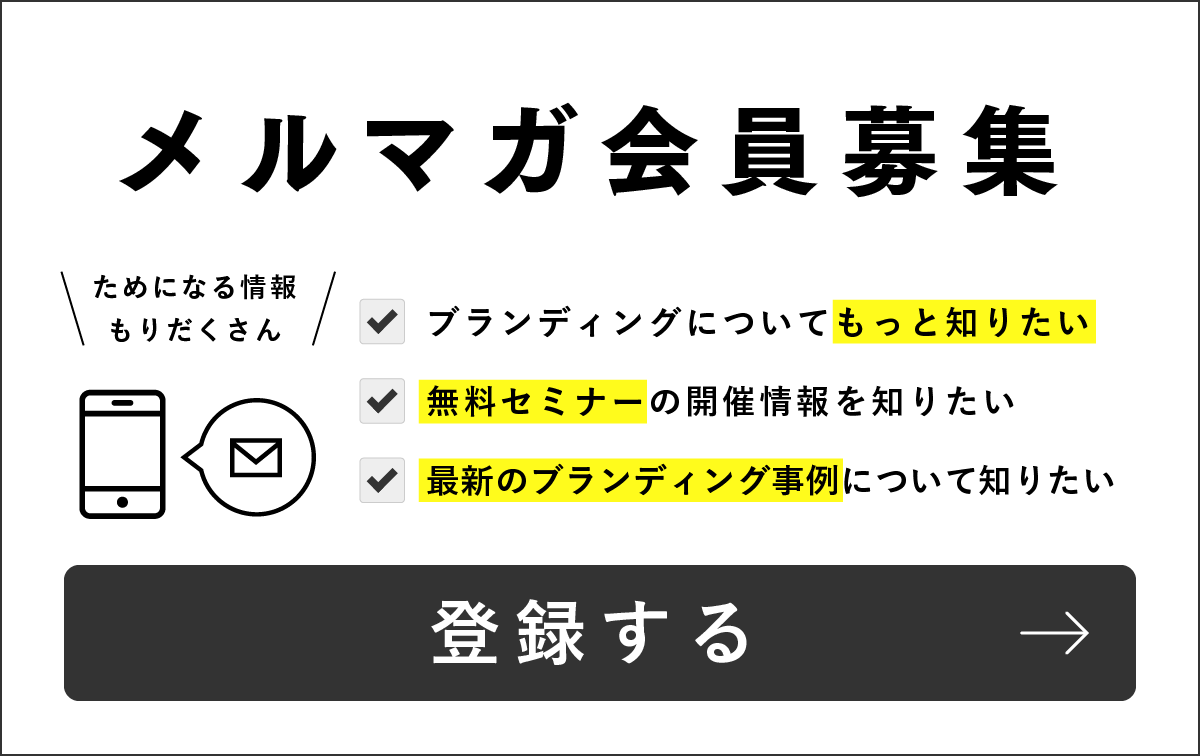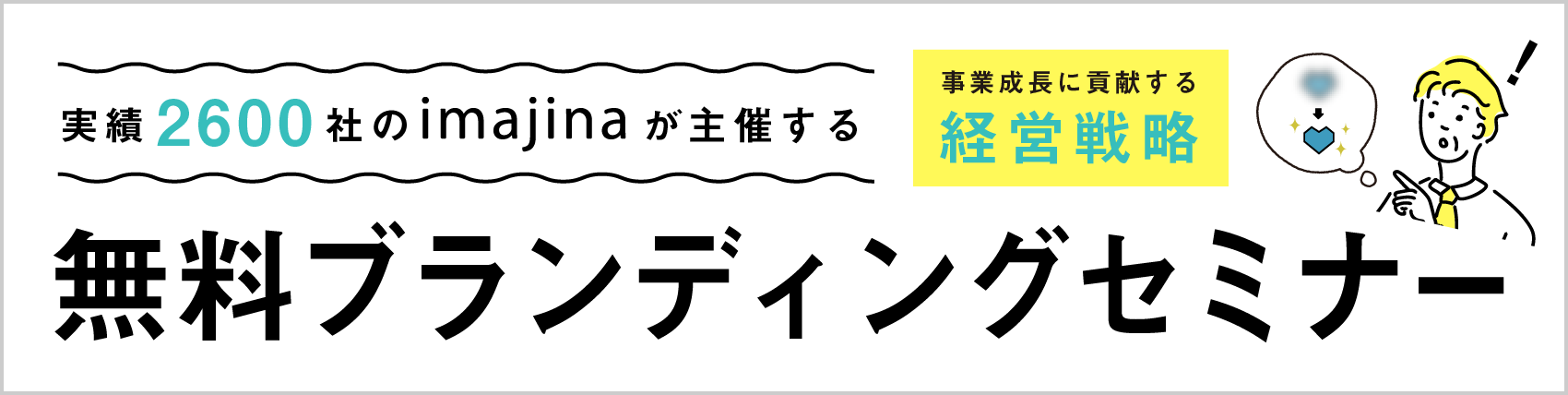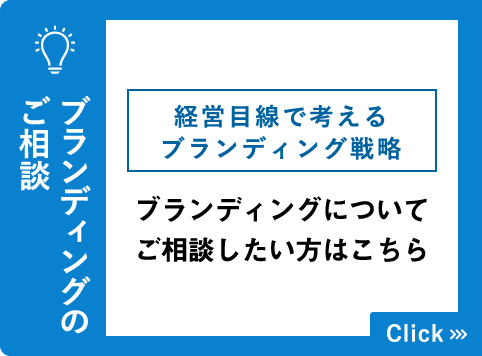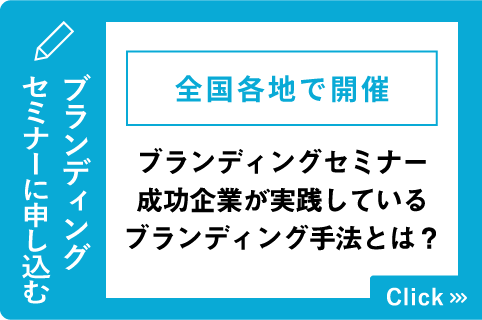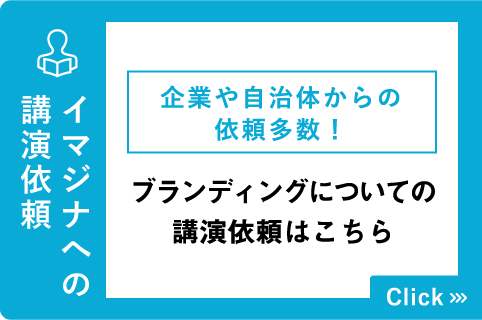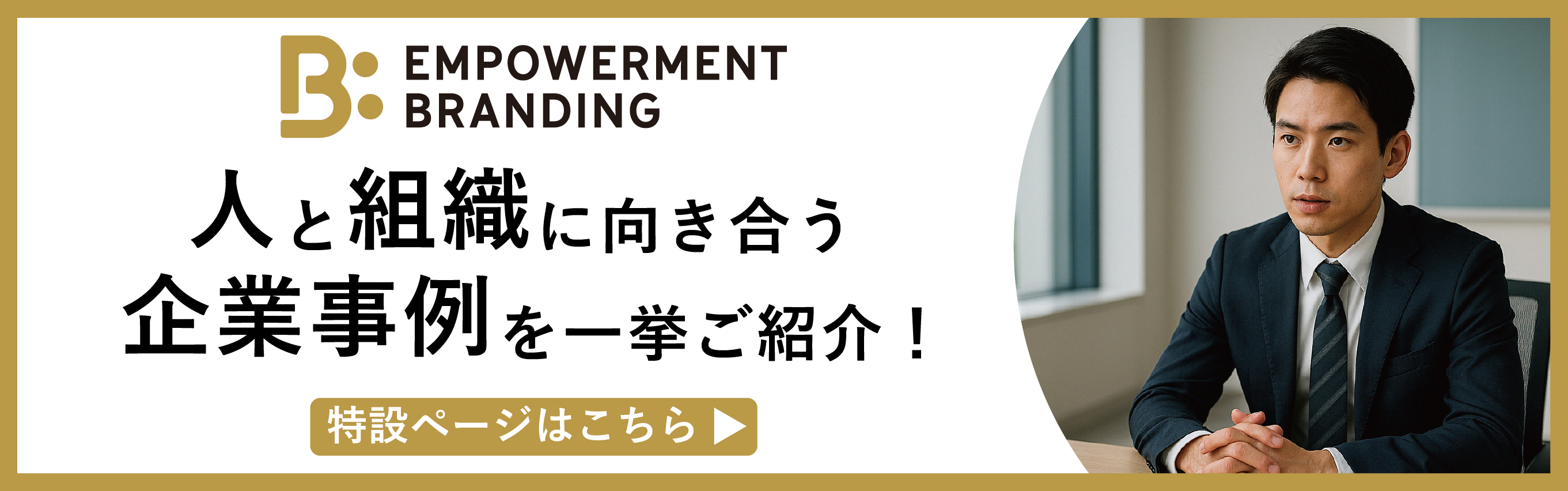「学ぶ」の語源は「まねぶ」、つまり「模倣する」という意味の言葉であることからもわかるように、私たちの「学び」の出発点はいつも「真似をすること」にあるといえます。
しかし、人は「真似をする」ことで毎回プラスの学びを得るものでしょうか?
決してそうではない、ということが、科学的な実験からもわかっています。
今回は、企業における「モデルケース人材」の重要性を、研究やデータをもとに紐解いてまいります。
■社会的学習理論(Social Learning Theory)とは
まずは、スタンフォード大学の心理学教授であるアルバート・バンデューラによって確立されたこちらの理論から見てまいりましょう。
「社会的学習理論」とは、人は自ら直接的に体験していない事象であっても、他者の言動を観察したり模倣したりすることで習得可能である、という理論です。
彼は、こうした人間の習性をいくつかの実験結果から導き出していますが、中でも特に有名なのが「ボボ人形実験」。
この実験では、起き上がりこぼし人形に対して大人が「A:木槌で叩く」「B:愛情をもって接する」「C:激しく罵倒する」という異なるパターンの遊び方をし、その様子をそれぞれ別の子どもたちに観察させます。実際に子どもたちにも人形を与えたところ、彼らは大人の遊び方を真似て人形に攻撃的になったり、あるいは優しくなったりしたとのことです。
このような実験から、人間は自分が体験していないことからも学習できるということがわかります。
さらに、このような人間の習性には「代理強化」という特性があると言われています。
他者の行動が賞罰によって強化される様子を観察・模倣することによって学習が深まる、という特性です。
例えば、宿題の範囲を間違えて多めにやってきた子どもが先生に褒められる。すると嬉しくなって、それ以降毎回、宿題を多めにやって提出する。それを見ていた周りの子どもたちも、真似して宿題を多めにやってくるようになる、といった形です。
人が他者を真似するときは、良い行動も悪い行動も模倣の対象となり得ます。
むしろ、悪い行動のほうが真似しやすかったりするものです。
しかし、上記の「代理強化」の考え方に基づけば、
良い行動をしている人がいて、その人を褒める(評価する)仕組みがあれば、良い行いも連鎖していくといえます。
このことは、組織成長において、モデルケースの存在と正しい評価制度が非常に重要であることを示唆しています。
■企業においてモデルケースはなぜ重要か
事実、モデルケースが多くいる環境ほど若手が前向きに働けることが、リクルートワークス研究所の調査でわかっています。
下記のグラフからも読み取れるように、若いときに強く影響を受けた人(=モデルケース)の数が多い人材ほど、現在の自分のキャリアに満足しています。
組織においてモデルケースとなる人材の有無が、若手のモチベーションや定着率に直結するのです。
しかし、企業の実情を見てみると、ロールモデルとなる人材はなかなかいないというのが現状です。
厚生労働省の「労働経済の分析」からは、「ロールモデルがいる」と答えた人の割合は25歳以上でガクンと下がっています。
社会人として多くのことを吸収できるこの年代の約7割にモデルケースがいないというのは、何とももったいない状況です。
同時に、企業は若手のキャリア満足を引き出せないような環境をつくってしまっているともいえるでしょう。
では、どうすれば企業のモデルケース人材を育成していくことができるのか。
その答えを、全国で開催中の「経営・ブランディングセミナー」で解説いたします。
企業におけるモデルケース人材に必要な条件とは何なのか?
モデルとなる行動を評価する仕組みはどうやってつくるのか?
そんなトピックをはじめとし、企業のモデルとなる「管理職」を中心に据えた人材戦略についてお伝えいたします。
ご興味のある方は、ぜひこの機会をご活用ください!