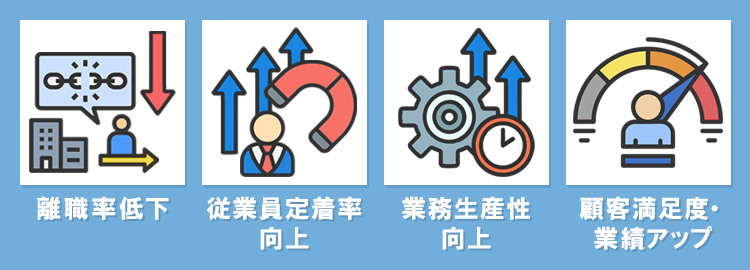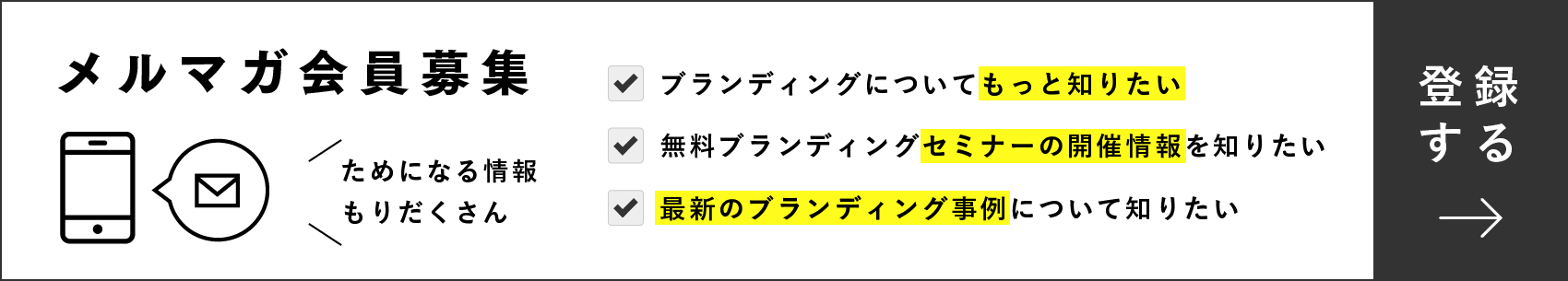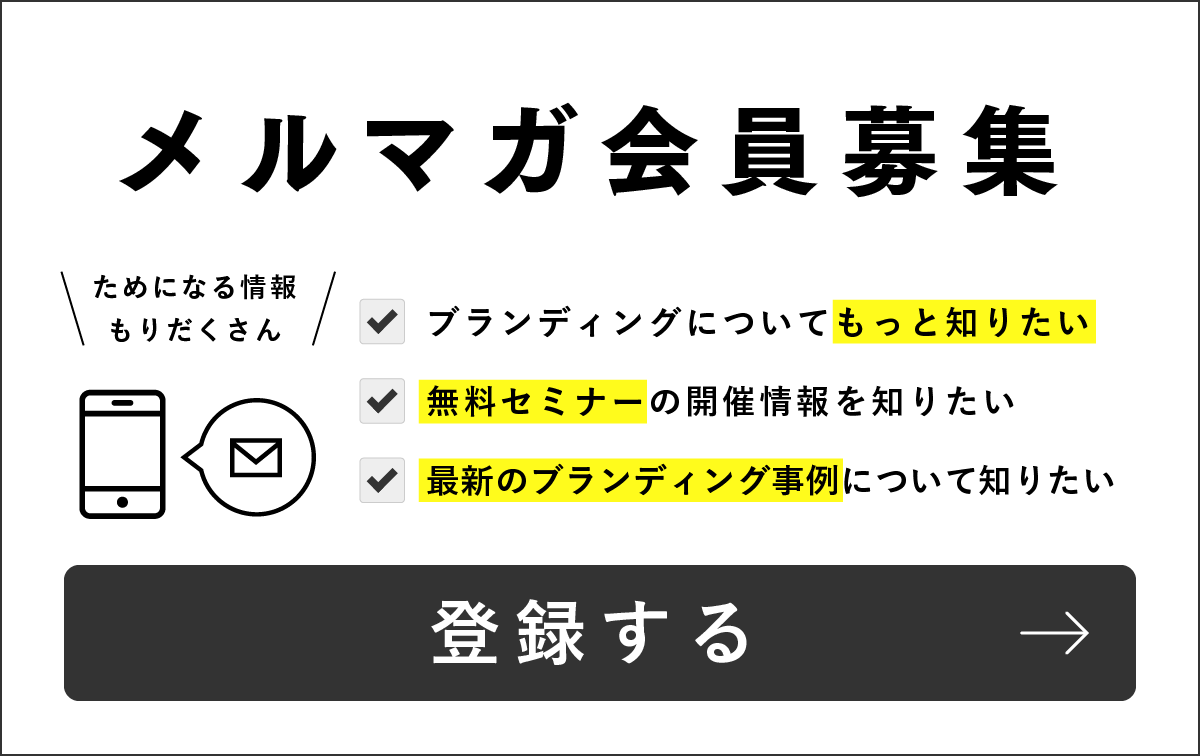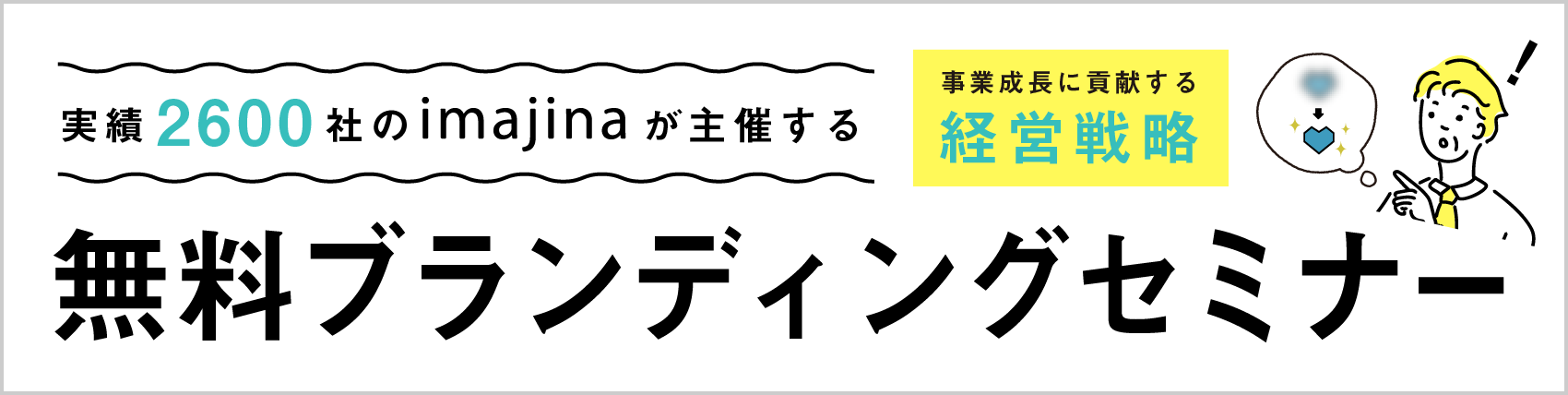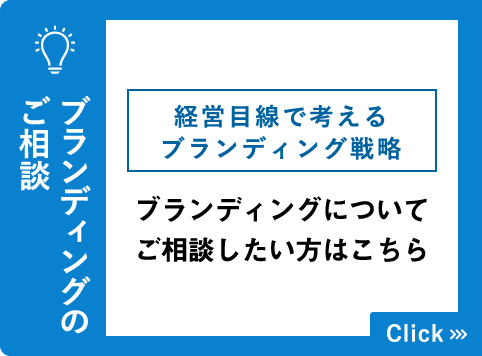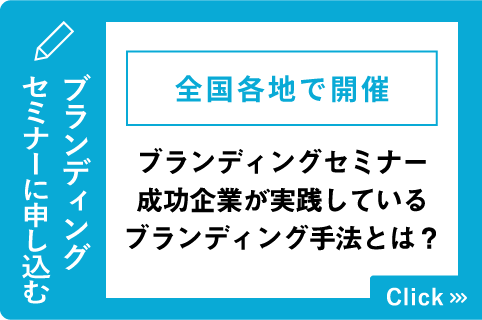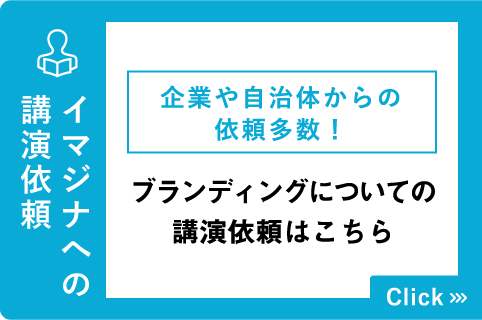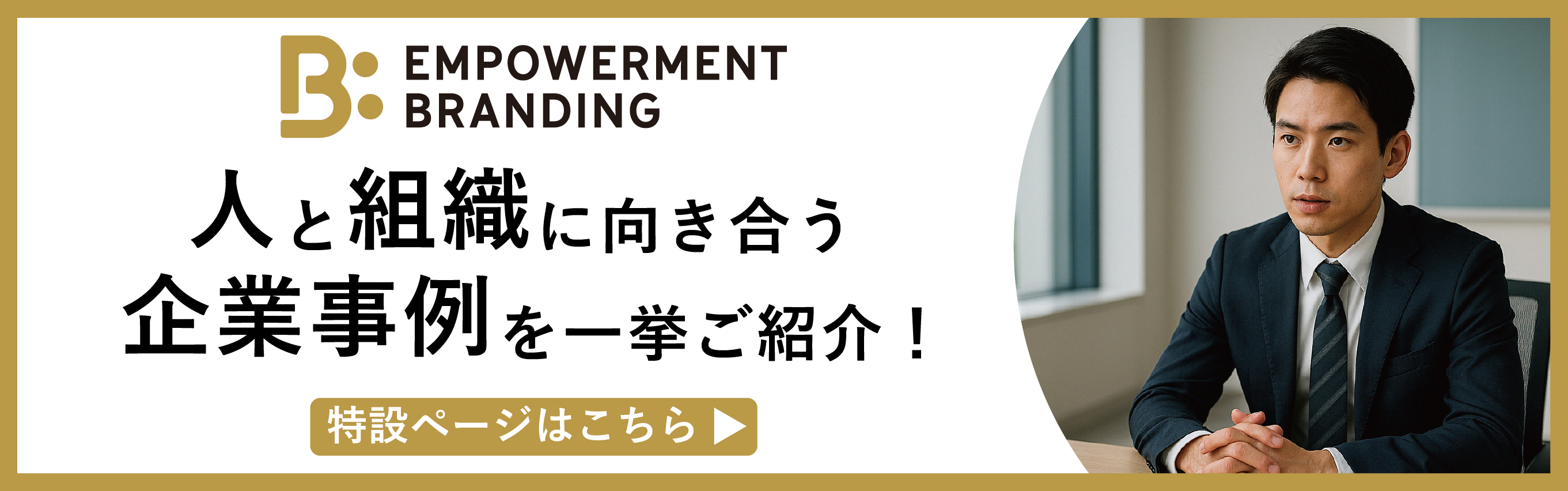INDEX [非表示]
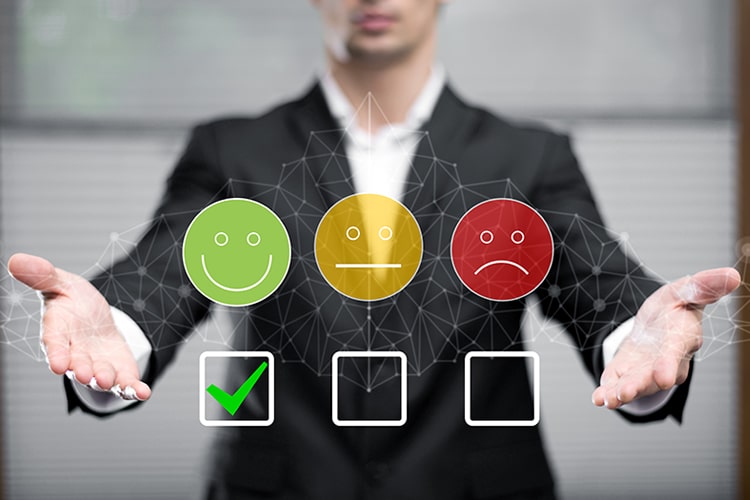
従業員満足度(ES)調査とは、職場環境や社内における人間関係などの要素で計測される従業員の満足度を、アンケートを通して調査することです。従業員満足度を高めると、離職率の低下や従業員の定着率向上につながるほか、社員個々のモチベーションが上がるメリットがあります。
当記事では、従業員満足度を高める基本的な要素をはじめ、調査の項目、調査方法などを紹介します。従業員満足度調査の基本的な情報を知りたい人や、アンケートの調査結果を施策に反映したい人はぜひ参考にしてください。
従業員満足度(ES)調査とは?
従業員満足度(Employee Satisfaction=ES)とは、待遇や福利厚生、マネジメント、職場環境、働きがいなどの要素で計測される従業員の満足度のことです。従業員満足度は離職率や生産性などに影響を与えます。社会全体で働き方改革への機運が高まるにつれて、社員から自社へのまなざしも厳しくなっており、従業員満足度はますます重要な考え方となっています。
従業員満足度を高める要素
従業員満足度は下記の要素で高めることができます。
- 企業ビジョンへの共感
- 評価制度への納得
- やりがい・貢献度
- 職場環境の快適度合い
企業によってすでに実現できている要素、できていない要素はそれぞれ異なります。自社に足りないものは何かを思い浮かべながら、読み進めていくとよいでしょう。
企業ビジョンへの共感
企業ビジョンへの共感がある社員は、会社に対する帰属意識が高い傾向にあります。企業のビジョンを社内で共有すれば、会社への帰属意識が強まり、日々の業務も「やらされている」と感じず、自発的に貢献しようとする気持ちが湧いてきます。
ただし、ビジョンの押しつけは満足度低下の原因となるため注意が必要です。あくまで従業員の自発的なコミットメントを促すように意識しましょう。場合によってはビジョンを見直す必要があります。企業の掲げるビジョンは、その企業の社会提供価値や存在意義を軸に、周りが共感し応援したくなるものに設定します。
評価制度への納得
どれだけ企業ビジョンに共感を示し、内発的動機付けによって業務に取り組んでいても、正当な評価が得られなければせっかくの自発性も挫かれてしまいます。しかし、評価制度に納得していれば会社に貢献した見返りが期待でき、働きがいも生まれます。そして、呼応するように従業員満足度も上昇するでしょう。
企業の掲げるビジョンと評価制度に矛盾があってはなりません。ブランドを形にし、ビジョンが明確になったら、それを評価制度に反映させていく必要があります。例えば、会社が何か大きな挑戦をすると決めたのに、評価制度で社員の挑戦を評価できていなければ、社員はビジョンを体現できません。
ビジョンに向かう行動をとっている人が、きちんと評価されるような制度設計にしていくことが、企業にとって重要になります。
やりがい・貢献度
「自分の仕事が社会に貢献できている」と感じられれば、仕事に意義を見いだすことができます。そのため社員に仕事と社会の接点を感じてもらうために、一人ひとりの仕事が、顧客からどのような印象を持たれているのか、社会にどのような価値を提供しているのかを可視化する仕組みをつくりましょう。
職場環境の快適度合い
職場環境には、福利厚生やライフワークバランス、職場の人間関係などが含まれます。福利厚生の充実やライフワークバランスの実現は私生活での満足度を高め、結果として会社に対する評価がアップし、従業員満足度の向上につながります。
給与や待遇などの金銭的報酬だけでは社員の一時的な満足度にしかつながりません。日々の業務に対するやりがいなどの非金銭的報酬によって、長期的な視点での社員満足度向上が達成できるでしょう。
また、お互いに刺激しあい、学びを得られるような良好な人間関係を社内で構築することによって、従業員満足度を上げることができます。
従業員満足度を高めるメリット
従業員満足度を高めると下記のようなメリットにつながります。
- 離職率の低下
- 従業員定着率の向上
- 業務生産性の向上
- 顧客満足度・業績アップ
ポイントは従業員満足度を高めることによって、中長期的なメリットを享受できることです。たとえば従業員定着率が向上すると、教育体制が安定し、優秀な人材が育成される好循環が生まれます。
では、上記の点を踏まえた上で、それぞれメリットを詳しく解説します。
離職率の低下
内閣府が2017年に行った「子供・若者の意識に関する調査」によると、初職の離職理由は1位の「仕事が自分に合わなかった」に次いで、「人間関係が良くなかった」「労働時間、休日、休暇の条件がよくなかった」が上位でした。
良好な人間関係やワークライフバランスの実現など職場環境の快適さは、従業員満足度に大きく影響します。したがって職場環境の快適さを高め、従業員満足度を向上させることは、離職率低下に直結するでしょう。
従業員定着率の向上
離職率が低下すれば、従業員定着率は向上します。従業員が安定して定着するようになると、人材採用のコストや教育コストが削減できるため、その分全体の生産性も高まります。また、優秀な人材の流出を抑えることによって、会社の業績の安定化にもつながるでしょう。
業務生産性の向上
従業員満足度が向上すると、仕事へのモチベーションも高まります。モチベーションが高い従業員は効率的に業務に取り組むため、生産性が高い傾向にあります。また、モチベーションが高い従業員同士はコミュニケーションも活発なので、連携が強化され、業務生産性に相乗効果を与えるでしょう。
顧客満足度・業績アップ
従業員満足度が高い企業の社員は、会社に対する愛着や自社製品・サービスへの理解度も高い傾向にあります。そのような社員は会社の顧客を大事にするため、自社製品の説明にも説得力が生まれ、結果として顧客満足度も向上します。
三菱UFJ リサーチ&コンサルティングは、2016年に企業の業績傾向に関する研究報告(厚生労働省委託)を実施しました。調査によると、評価制度の見直しやワークライフバランス実現のための取り組みを早期に行っている企業ほど、業績が増加傾向にあります。
従業員満足度は一見業績とは関係なさそうに見えるものの、中長期的な視点に立つと盤石な会社づくりを下支えする重要な要素と言えます。
従業員満足度調査の項目
従業員満足度は、アンケート調査のデータをもとに分かりやすく可視化できます。従業員満足度調査(ES調査)を行うにあたり、まずは調査内容を把握することが大切です。調査結果を社員の定着率アップや会社の発展につなげるために、項目ごとにしっかりリサーチしましょう。
ここでは、従業員満足度調査の主な調査項目を解説します。
仕事満足度
仕事満足度は、社員が実際に行っている業務内容に対する満足度合いを調査する項目です。
仕事満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
| 仕事内容満足度 |
|
|---|---|
| 自己成長満足度 |
|
| 仕事継続満足度 |
|
仕事内容満足度と自己成長満足度は、今後も仕事を続けたいと思うかどうかにつながる項目と言えます。
職場満足度
職場満足度は、社員が働きやすい職場環境で働けているかを把握するための項目です。
職場満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
- 職場内で情報を共有できているか
- 職場での人間関係は円滑か
- 社員同士で協力し合えているか
- 福利厚生の内容に満足できているか
職場満足度は、社員のストレス要因を探る役割もあります。職場環境に対する満足度が低い場合は、課題解決に向けた対策が必要です。
上司満足度
上司満足度は、上司のマネジメントや言動に対する満足度合いを調査する項目です。
上司満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
- 仕事に対する上司からの指示は適切か
- 上司のフィードバックは適正か
- 上司から十分なサポートを受けられているか
- 上司からの信頼を得られているか
上司満足度は、社員が求める上司像を把握したり、パワハラの原因となる行動を探ったりするのに役立ちます。
処遇満足度
処遇満足度は、会社からの評価や給与面などの処遇に対する満足度を把握する項目です。
処遇満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
| 人事評価満足度 |
|
|---|---|
| 給与等満足度 |
|
| 個人目標満足度 |
|
| 労働時間満足度 |
|
処遇満足度の基準は、給与の高さや低さだけではありません。処遇満足度が低い場合、社員が評価・給与・目標設定・労働時間に不満を抱いていることを意味します。
福利厚生満足度
福利厚生満足度は、社員に対して十分な福利厚生を提供できているか調査する項目です。
福利厚生満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
- 勤務形態の自由度が高いか
- 退職金や年金の制度が整っているか
- 慶弔についての配慮があるか
上記以外にも、各種補助・ライフサポート・旅行など、法定外福利厚生の充実度が福利厚生満足度に影響します。社員のニーズに合った福利厚生を提供することは、人材確保や社員の定着率アップに効果的です。
経営満足度
経営満足度は、会社が掲げるビジョンや経営方針に対して社員が感じている満足度を示します。
経営満足度を構成する要素の具体例は、下記の通りです。
- 会社の理念や経営方針に共感しているか
- 会社の将来性に不安を感じていないか
- 自社製品やサービスに誇りを持っているか
社員が経営陣に対して、経営に関する思いや本音を伝える機会はほとんどありません。経営満足度を把握することは、会社と社員が同じ方向を向いて進めているかを知るきっかけにもなります。
総合満足度
総合満足度は、仕事・職場・上司・処遇など会社を総合的に見た場合の満足度です。項目ごとに不満な点や不十分だと感じる点があったとしても、総合的には満足しているという社員も少なくありません。
総合満足度を高める主な方法は、下記の2つです。
- 社員の不満につながっている項目を改善する
- 社員の満足度向上につながる項目に力を入れる
まずは、仕事や職場、上司などに対する従業員満足度を調査して現状を把握しましょう。
従業員満足度の調査方法
従業員満足度の調査は主にアンケートを通して行われます。具体的な流れは下記の通りです。
- 1. 調査目的を明確にする
- 2. 質問項目の設計
- 3. 回答を依頼
- 4. 回答の集計・分析
- 5. 経営層へ報告
- 6. 社員へフィードバック
- 7. 向上に向けた施策の実行
- 8. 定期的な調査
1~8は必ずしも一方通行的なステップではありません。「8.定期的な調査」によって施策がうまくいっていないことが明らかになれば、「4.回答の集計・分析」や「2.質問事項の設計」に立ち戻る必要があります。
それでは各手順を詳しく見ていきましょう。
調査目的を明確にする
まずは調査目的を明確にしましょう。何のために調査するのかがはっきりしていなければ、調査結果の有効活用が行われず、ただアンケートを採っただけという状況になってしまいます。さらにアンケート調査が職場改善に反映されていないと分かると、社員の不満を増長させかねません。
質問項目の設計
質問項目は最初のステップで定めた調査目的に対応したものを用意しましょう。調査目的と質問事項に対応関係がない場合、どこをどう改善すれば良いのかがぼやけてしまいます。そのような事態を避けるためにも、質問事項の設計の際は「この質問は何のために行うのか」「質問項目同士に関係性はあるか」といったことを吟味しましょう。
また、「不満があるところを教えてください」というような質問の仕方ではなく、「どうすればもっと良くなると思いますか?」というようなポジティブな印象を与える表現にしたほうが効果的です。ネガティブな質問は、それだけで従業員に自社のネガティブなイメージを想起させるためです。
回答を依頼
質問事項の設計を終えたら実際に回答を依頼します。いきなり回答してもらうのではなく、あらかじめ「アンケートを実施すること」や「調査目的は何か」「どのように活用していく予定か」といったことを説明しておくことが重要です。
おそらく誰でも、アンケートに適当に答えたという経験があるでしょう。モチベーションがなければ当然です。そのため、事前説明によってアンケートに答えるモチベーションを引き出す必要があります。十分な動機付けによって行われた回答は有効性が高く、調査結果もより実態に近いものとなるでしょう。
回答の集計・分析
回答期間が終了したら、集計・分析を行います。アンケートの集計・分析法は大きく分けて下記の3つです。
- 単純集計
- クロス集計
- 満足度構造分析
単純集計は設問ごとに集計を行います。単純集計は会社の強みなどを把握できるため便利ではあるものの、具体的な改善策を練るのには大雑把すぎるのが特徴です。
課題を浮き彫りにするにはクロス集計が役に立ちます。クロス集計は性別や年代といった回答者の属性に分けて集計を行うため、性別による満足度の違いや、役職ごとのギャップを把握できるのが特徴です。部署ごとに満足度の差が激しい場合、部署間連携に問題があるのではないかと課題が見えます。
満足度構造分析は満足度の度合いごとに、設問間でどのような相関関係があるのかを分析します。たとえば「総合的に満足度が高いグループの回答にはどのような一般傾向があるのか」を調べることによって、従業員満足度を高めるための手がかりを掴めるでしょう。
経営層へ報告
アンケート結果にもとづいて分析が終わったら、対策を検討・立案します。対策を検討する際は、調査の目的に合わせて個人や組織ごとに見ると対策が立てやすくなります。
対策を立案した後は経営層に結果を報告して、施策を実行してもよいかの確認をとりましょう。経営層に報告するときは、調査の全体像だけでなく良い部分と悪い部分にも触れ、対策すべき内容を説明するのがポイントです。
社員へフィードバック
経営層への報告を終えたら、次は社員にもフィードバックを行います。集計結果や分析によって明らかになった課題点、今後の大まかな方針などを周知しましょう。
せっかく社員にアンケートに答えてもらって、集計したのにもかかわらず、その結果や改善施策を社員に報告することを怠ってしまうと、社員からの印象が悪くなってしまう可能性があります。
向上に向けた施策の実行
従業員満足度向上のための施策は、調査からあまり時間をかけずに実行に移しましょう。会社の状況は刻々と変化しているので、対策が遅れてしまうとアンケート実施時点とは別の問題点が生じている可能性があるためです。調査・分析により導き出した施策の効果を最大化するためにも、迅速な行動が欠かせません。
定期的な調査
施策を実行に移した後は、実際に効果を上げているのかを定期的に調査する必要があります。なお再調査の際は、記述式の質問事項を用意して社員のリアルな声を集めるとよいでしょう。施策の浸透度がより明確になります。
期待していた成果が得られなかった場合は、分析に問題があるか、質問事項の設計ができていない可能性があります。会社独自で行っていたのならば、外部リソースを利用することも検討しましょう。
従業員満足度を高めるためには?
従業員満足度を高めるためには、人事部だけでなく経営層も従業員満足度の調査結果を把握する必要があります。従業員満足度調査の実施方法に悩んでいる場合は、従業員満足度調査ツールを利用したりプロに相談したりする方法もあります。改善すべき問題点や課題点を理解し、適切な施策を実施して会社全体で従業員満足度の向上を目指しましょう。
ここでは、従業員満足度を向上させる施策のポイントについて具体的に解説します。
ビジョンを共有する
従業員満足度の向上には、社員とのビジョン共有が大切です。人事部や経営層が考えた施策を実行する前に、まずは社員に目的や方向性を分かりやすく伝えます。
意見を出した社員にはインセンティブを与えるなど、ビジョンに合った行動を評価する仕組みを構築することも効果的です。評価制度を明確化するために、人事制度の見直しにも取り組みましょう。
会社と社員が同じ方向を向いて進むことで組織としての一体感が生まれ、会社に対する将来への期待感が高まる効果が期待できます。
社員同士のコミュニケーションを増やす
従業員満足度の向上のためには、社員同士のコミュニケーション促進も重要です。
社員同士のコミュニケーション促進の具体例は、下記の通りです。
- 社員食堂やフリースペースの設置
- 社員参加のイベントの企画
- 社内研修会や勉強会の開催
- 定期的にランチ代を支給
- ブラザー制度の導入
社員同士が交流できる機会を積極的に設けることで、部署外の社員とのコミュニケーションも図りやすくなります。
ブラザー制度は、新入社員の相談に乗るために先輩社員がサポート役につく仕組みです。新入社員の悩みや不安を軽減しつつ、コミュニケーションも増やせます。
福利厚生や職場環境を見直す
福利厚生や職場環境の見直しは、従業員満足度の向上に効果的です。
福利厚生や職場改善の具体例は、下記の通りです。
- 法定外の休暇を用意する
- 補助制度を充実させる
- オフィスマッサージを提供する
- 無駄な残業を見直し削減する
- 職場環境を整備する
ただし、従業員が求めている福利厚生や職場環境には個人差があります。社員の年齢層やニーズを考慮した上で、会社と社員にメリットとなる取り組みを検討しましょう。
職場環境の改善は、計画を立てて実践するだけでなく、検証と改善までを一連の流れとして捉えることが大切です。PDCAを回すことで、より快適な職場環境を目指しやすくなります。
従業員エンゲージメントとはどう違うのか?
従業員満足度と混同しやすい言葉に、「従業員エンゲージメント」と呼ばれるものがあります。従業員エンゲージメントとは、従業員の自発的貢献の度合いや、会社にどれだけ愛着を抱いているかを示す指標です。
従業員満足度と従業員エンゲージメントはどちらも、「離職率の低下」や「業績アップ」につながる点で共通しているものの、アプローチの仕方には違いがあるのが特徴です。同じメリットを追求するとしても、従業員エンゲージメントでは「会社と社員の結びつきの強化」を通じて行い、従業員満足度では「満足度アップ」によって行われます。
アプローチの仕方の違いは、アンケートの質問項目に顕著に表れます。両者の特徴的な質問例は下記の通りです。
【従業員エンゲージメント調査の質問例】
- 仕事を探している友人や知人、親族に自社を勧めたいですか?
- 仕事をしていると時間が経つのを早く感じますか?
- 組織全体における戦略目標を理解していますか?
【従業員満足度調査の質問例】
- 昇進や昇級の頻度は適切だと感じますか?
- コンプライアンスは守られていますか?
- 勤務時間や残業時間は適切だと感じますか?
取り上げた質問以外では、重なるものもあります。しかし、待遇や労働条件に関する質問は、従業員満足度調査のほうが多く見られます。対して従業員エンゲージメント調査では企業との関係性を問う質問が多いです。
従業員エンゲージメントについてより詳しく知りたい人は、「従業員エンゲージメントとは?重要性や高める方法について解説」の記事を参考にしてください。
まとめ
従業員満足度調査(ES)とは、職場環境や働きがいといった従業員の満足度をアンケートによって調査することです。調査項目には仕事満足度や職場満足度、福利厚生満足度などがあるため、項目ごとにリサーチして社員の定着率向上や会社の発展につなげましょう。
株式会社イマジナでは、経営者や役員向けの無料ブランディングセミナーを実施しています。従業員満足度の向上を図りたい人や事業成長のコツを知りたい人は、ぜひご参加ください。