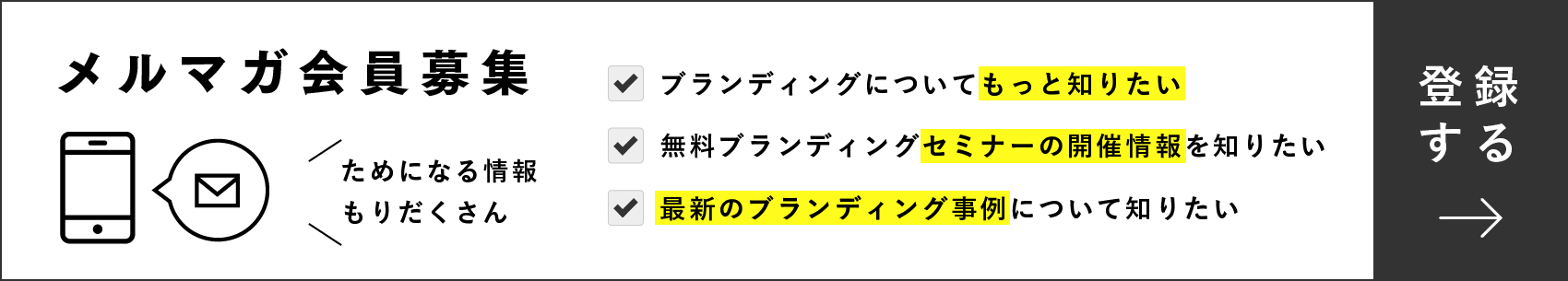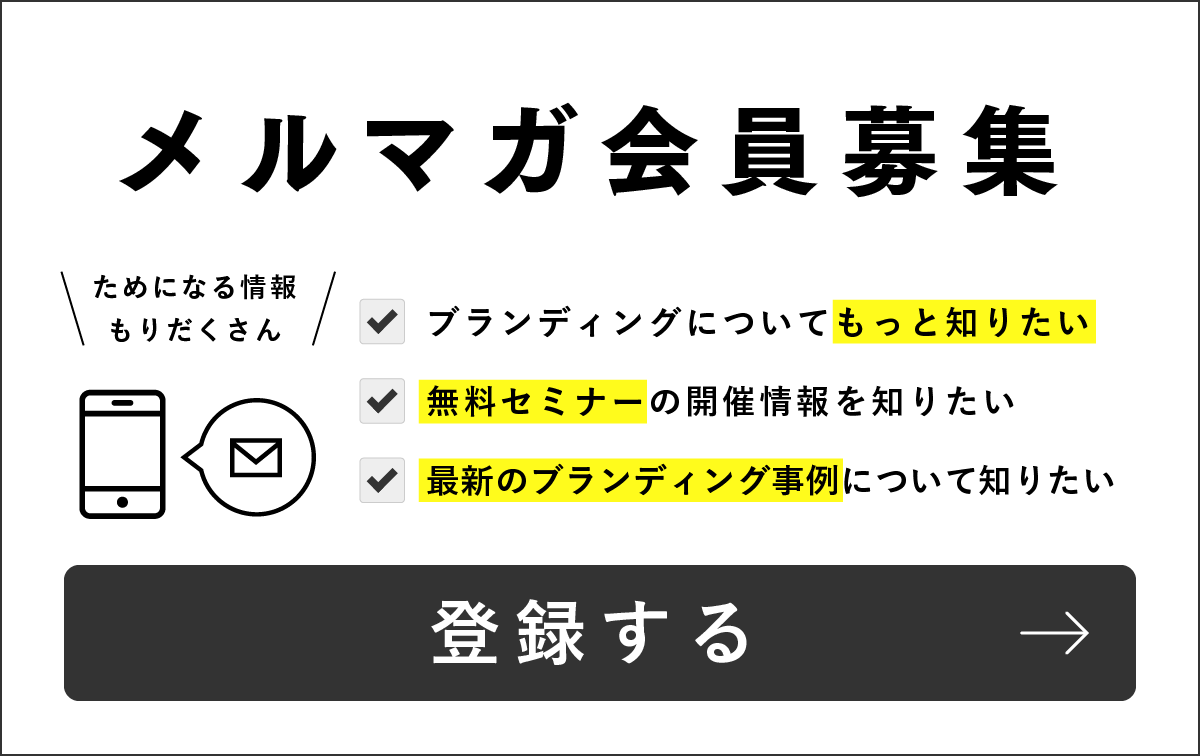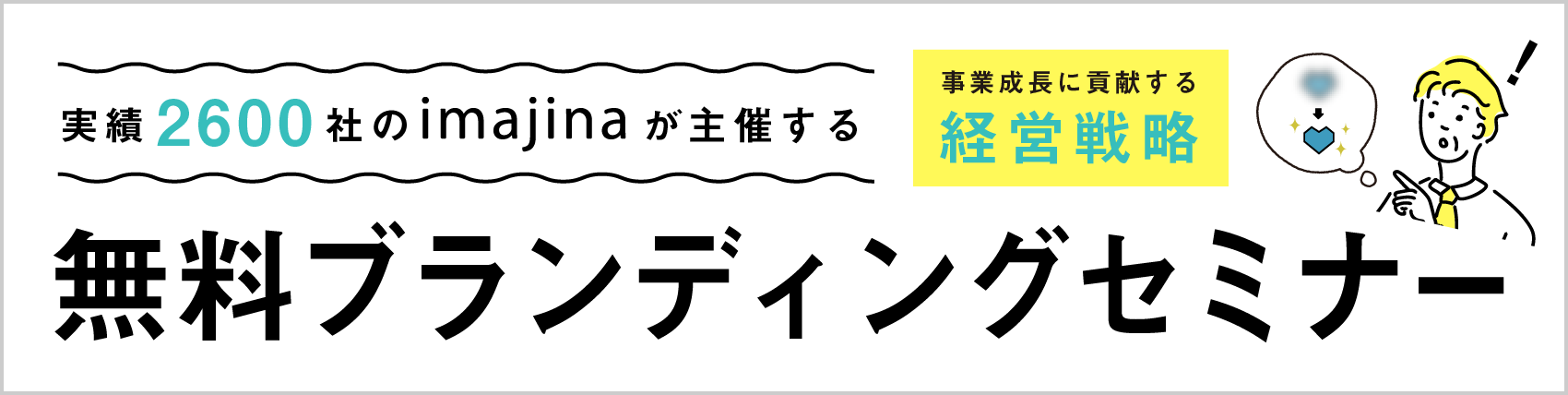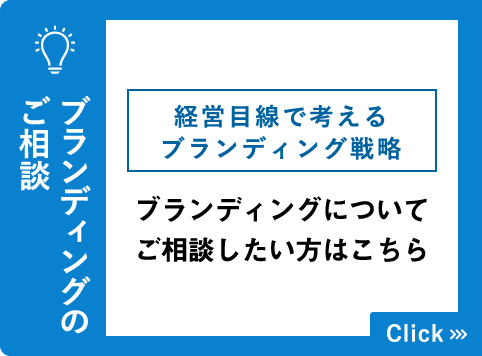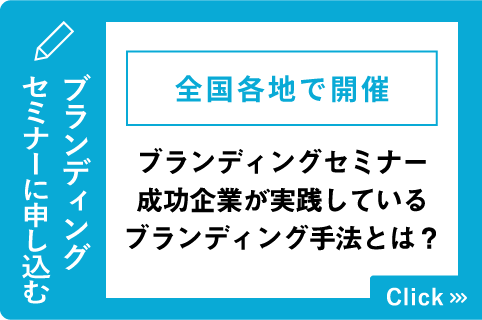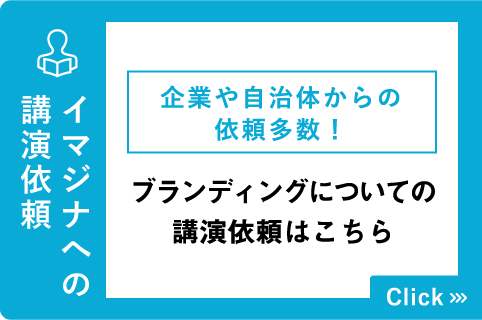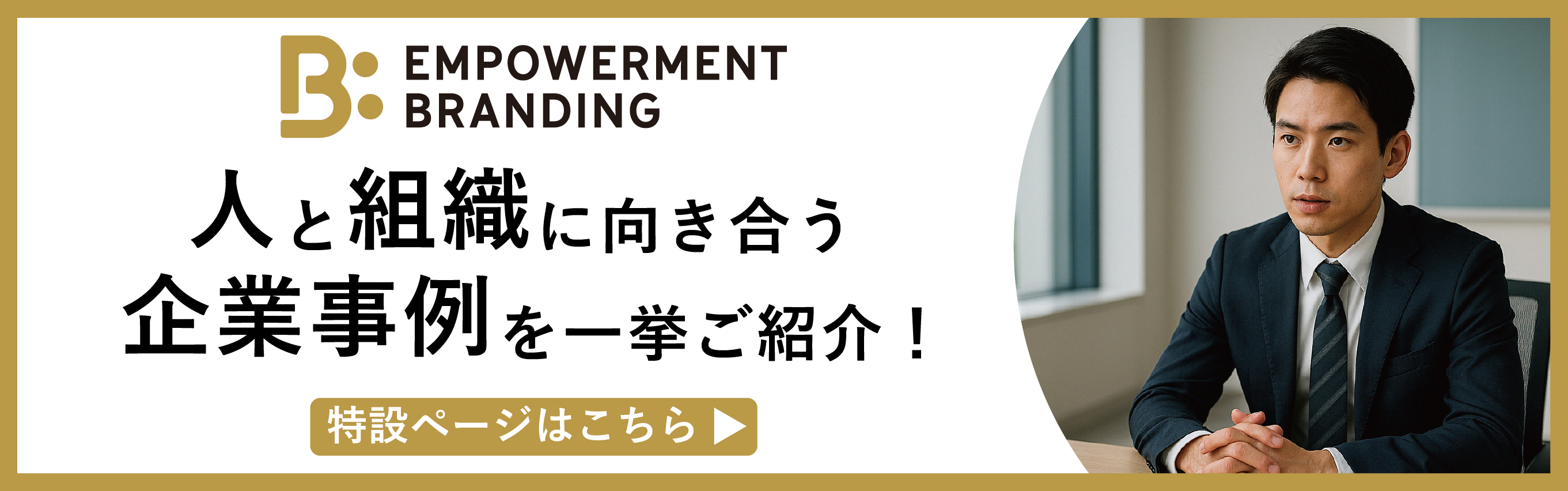皆さんは、テレビゲームやスマホゲームなどをされることがありますか?
休みの日にやることがあるという方も、自分自身はしなくても子どもが夢中になっているという方もいらっしゃるでしょう。
ゲームの世界は、日々進化しています。
そして新しいものが出るたびに、世界中のプレイヤーが熱狂し、虜になっています。
人はなぜこれほどまでに、ゲームに“ハマる”のでしょうか。
実は、そこには脳科学や心理学に裏打ちされたある仕組みがほどこされているのです。
その仕組みとは、「難易度の設定」。
今日は、この「ゲーム難易度」から、マネジメントにおいて非常に重要なポイントを掘り下げていきましょう。
ゲーム難易度のつくり方
ゲームにおいて不可欠な要素、それが「難易度」。これが適切に設定されていなければ、ゲームの面白みは半減どころではありません。
あまりに簡単な構造では張り合いがなく、すぐ退屈になって飽きてしまうでしょう。逆に一向にクリアできないとなると、「自分には無理だ、やーめた」と匙を投げてしまいます。
難易度のバランスがちょうどいいからこそ、流行りのゲームは人をテレビやスマホの画面に釘付けにしてしまうのです。
そしてゲームの難易度を設定する方法には2種類あります。
1つは、「静的難易度設定」。
これは、あらかじめ難易度が複数段階に設定されていて、プレイヤーは好きなレベルを選んでプレイできる、というもの。
「太鼓の達人」などをイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。
選んだ難易度でゲームを開始すると、そのゲームの間、難易度に変化はありません。
2つ目は、「動的難易度調整」。
こちらの方法では、プレイヤーの失敗回数やプレイスタイルに基づき、敵の強さ・数などが自動で調整されていきます。そのため、上手い人であれば敵がうじゃうじゃと出現したり、逆に数回ミスを重ねていれば敵の数がやや抑えられたり…といった加減が発生するのです。
これにより、プレイヤーごとの習熟度に難易度をアジャストすることができます。
また、基本的に人は一回のゲームをプレイする中でもだんだんと慣れて上手くなっていくため、慣れに合わせて少しずつ難しくなっていく仕様ともいえます。
これら2タイプの難易度設定のうち、よりプレイヤーを夢中にさせやすいと言われているのが、「動的難易度調整」。
その理由は、「実力ぴったり」の難易度でプレイできるからではありません。
難易度が本人の実力からやや高めに調整され続けることで、プレイヤーがずっと「小さな挑戦」を積み重ねることができるからです。
ちょっと難しい、でも頑張ればクリアできる。
そんな絶妙な関門をいくつも設けることで、プレイヤーの集中力と自己効力感はどんどん高まり、ゲームに没頭してやめられなくなる「フロー状態」がつくられていくのです。
いかに日々「フロー状態」を生み出すか
この「フロー状態」はゲームだけにいえるものではありません。
日々の仕事も、フロー状態に入ることで数倍、数十倍楽しめるものになります。
そしてそこには、適切な「目標設定」が不可欠なのです。
ゲームの例で見たように、努力すればなんとか達成できそうな程よい難易度の目標があることで、人間のモチベーションは段違いに上がります。
そしてそれをクリアし、また次の目標に向かうことができれば、さらに自信がつきます。
しかし、人はなかなか自分で「ちょうどいい目標」を立てられないものです。
「失敗するくらいであれば、到達しやすい簡単な目標を立てておこう…」
それが無意識に行われてしまうのが、人間の脳の怖いところ。
だからこそ、ゲームと同じように「難易度の調整機能」が必要です。
そして調整役を担うのは、他でもない管理職・上司の皆さんです。
本人の実力が今どのくらいか、どんなプレイスタイルを好むか?
それをしっかりと観察し、本人が挑戦できそうな幅で少し難しい目標を立てさせるのです。
そして、部下・後輩がその絶妙な壁を突破したときにこそ、「自分だってやればできるんだ!」という自己効力感、そして、「あの人の言う通りに挑戦してみてよかったな」という、あなたとの強力な信頼関係が生まれるはずです。