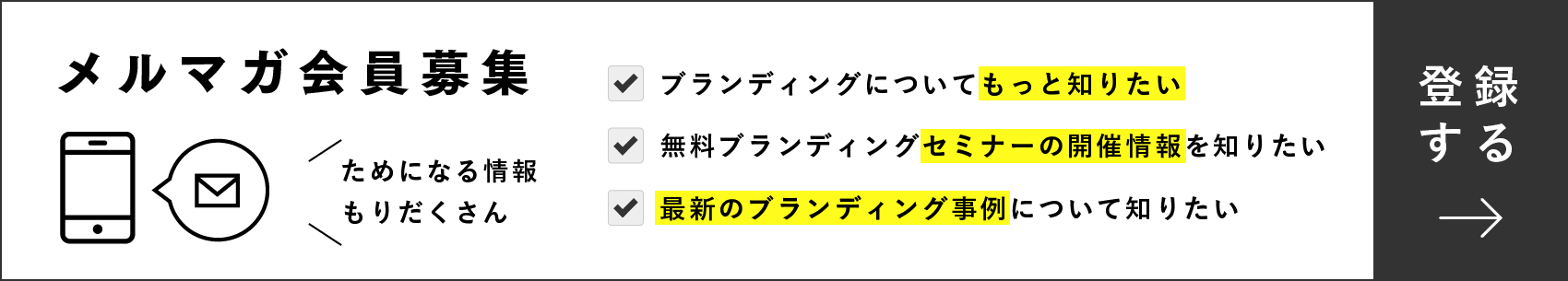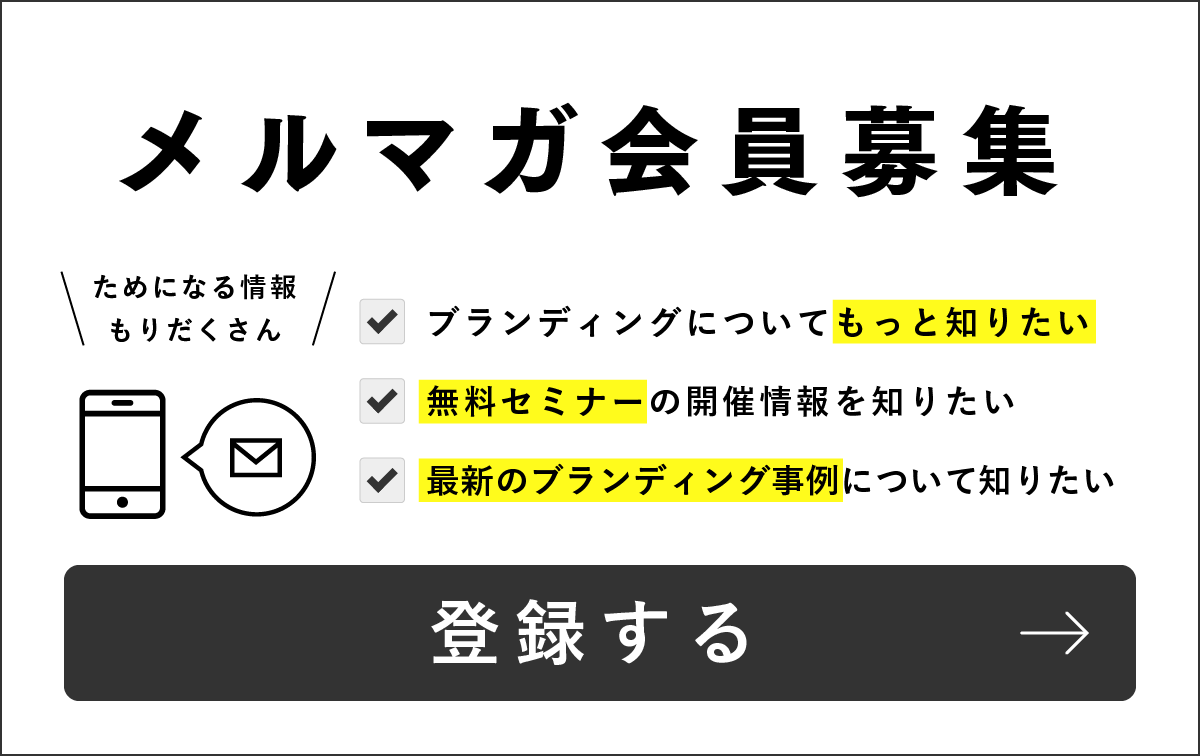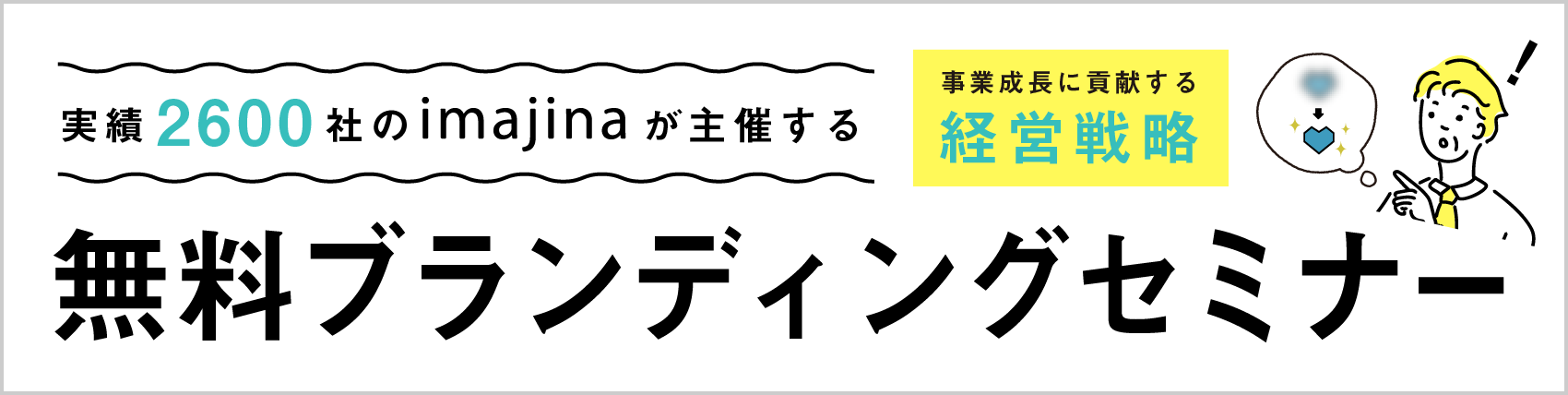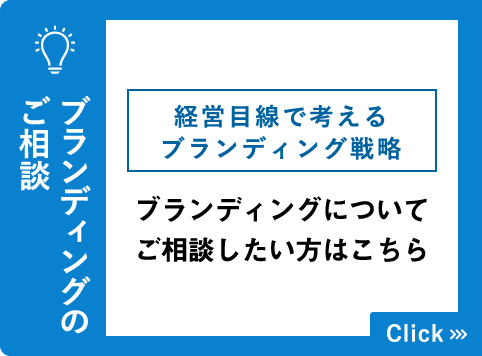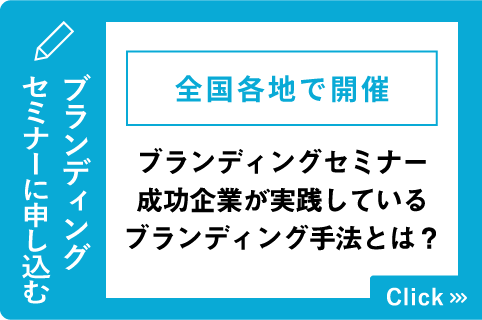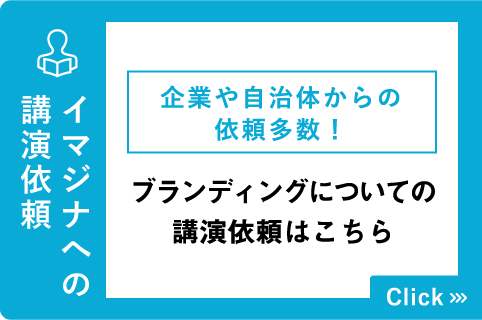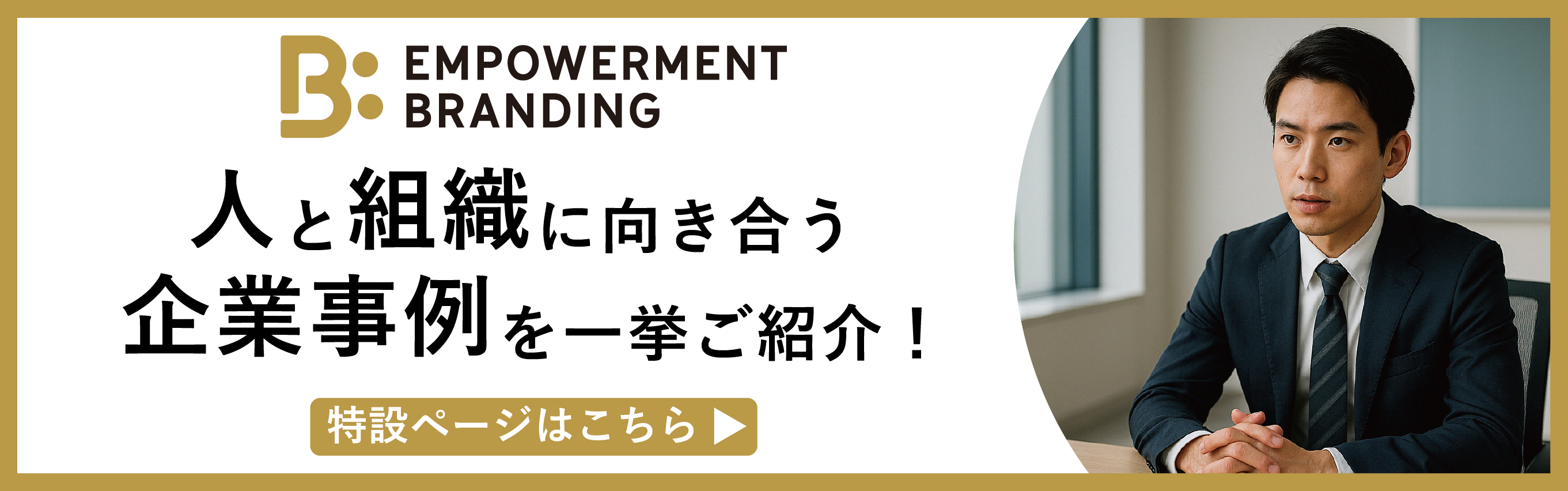終業時間も近づき、夕食のことや家族のことが自然と頭に浮かんでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
人間の脳は、あるときは一つのことに集中したり、あるときは余計なことをあれこれと考えたり、そういったモードの切り替えを無意識のうちに繰り返しているものです。
このような「脳のモード変換」について、マサチューセッツ工科大学やロンドン大学をはじめとした様々な機関によって研究がなされています。今日はその一部をご紹介しましょう。
代表的な脳のモード2つ
脳科学においてよく研究されているのが、「タスク・ポジティブ・ネットワーク」と「デフォルト・モード・ネットワーク」という2種類の脳の状態です。
これらの切り替えにおいて一つの契機となるのが、「目的の有無」。
一つずつ見ていきましょう。
タスク・ポジティブ・ネットワーク(TPN)
こちらは、明確な目的があるときによく働く脳機能です。注意を集中させ、目的・目標に向けた行動を起こすことが可能になります。
集中するとなると脳のエネルギーを多く消費しそうなイメージがありますが、実は意識を働かせるべき対象が一点に定まっているため、逆にエネルギー消費を最小限に抑えられるといわれています。
デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)
上記のTPNとは逆に、目的がないときはこのDMNが作用します。自由な思考に向かいやすいため、柔軟にアイデアを出したりするのには比較的向いている状態といえます。
しかし、目的を定めず自由に考えるということは、裏を返せばあれこれ気が散って余計なことまで考えてしまうということ。特に、内省的な思考を促す傾向にあるため、ネガティブになりやすいともいわれています。抑うつ傾向がある人は、このDMNが続いている状態にあるのです。
そして、このDMNは脳のエネルギーの60~80%を占めることもわかっています。目的がなく自由な状態は、かえって人の脳を疲弊させてしまうということです。
この2つのモードは、人間が生きていく上でどちらも欠かせません。
しかし、DMNの状態があまりにも長く続くと、人はどんどんとネガティブな思考に陥り、同時に脳を疲れさせてしまいます。
たとえば仕事の際に、部下の脳内でDMNばかりが多く作用してしまったとしたらどうでしょうか。きっと気が散って業務が捗らないのはもちろん、問題に対して前向きに解決策を考えることも、やる気を出すことも難しいでしょう。
脳のモードを最適化させ、TPNの働きを最大限活用するために必要なのは、皆様から部下へしっかりと「目的」を説明すること。
明確に目指すべき対象があれば、脳のリソースをそこに絞ることでより効率的に思考することができます。そうすれば、アウトプットの正確性が上がるだけでなく、余った脳のエネルギーを別の業務に割いて、さらなる付加価値を生み出していくことも可能になるのです。
このように、目的を明確化することは、脳機能の観点からみても非常に重要です。
全国で開催の「経営・ブランディングセミナー」では、目的を共有する際の伝え方や、その目的に向かってどのように部下を動かしていくべきかといったマネジメント手法についてお伝えいたします!