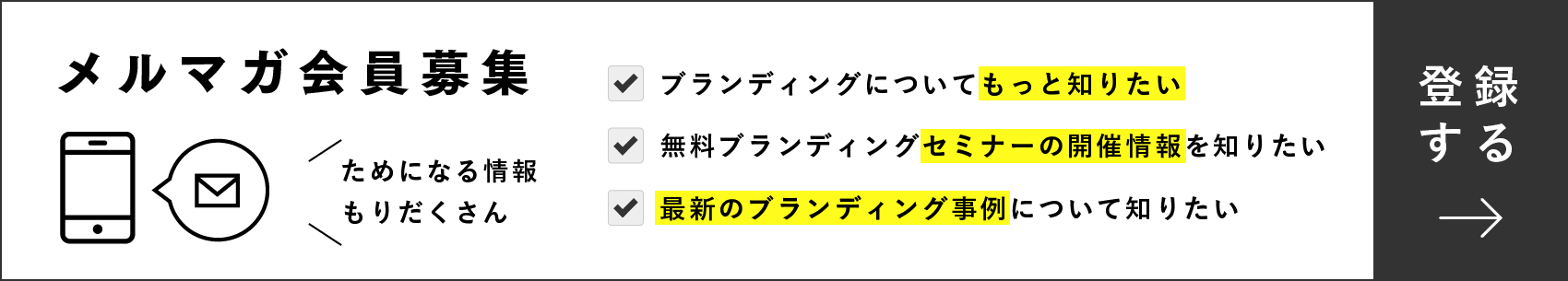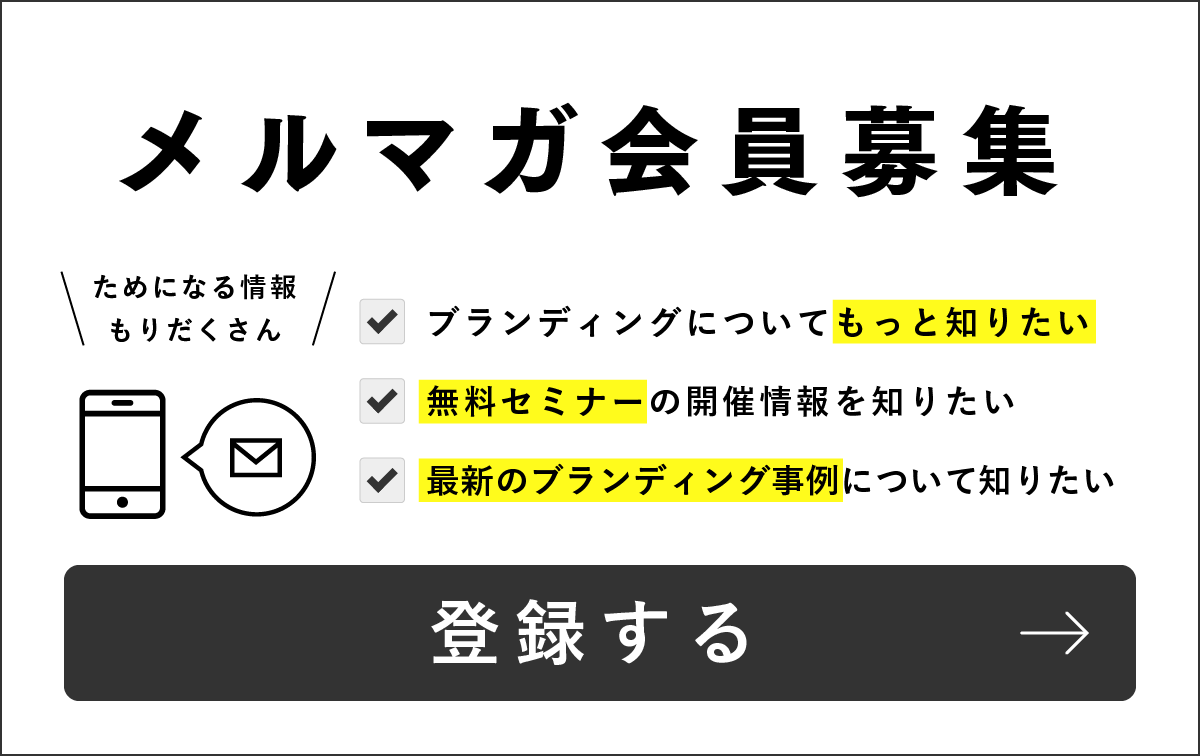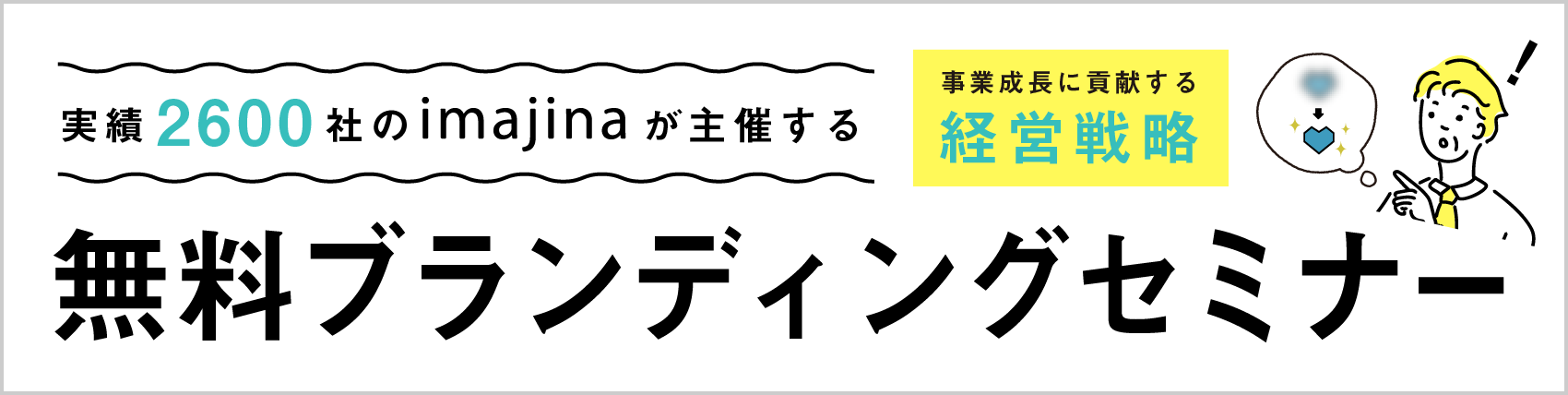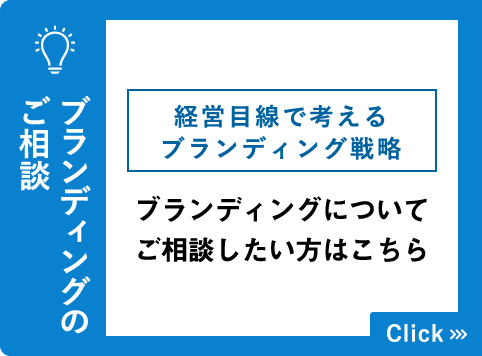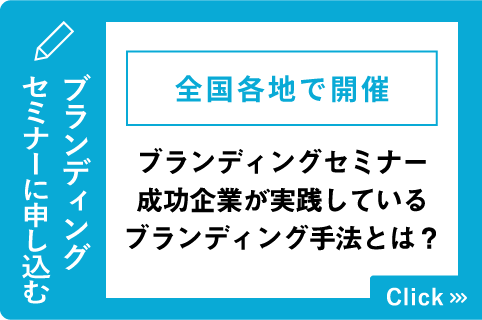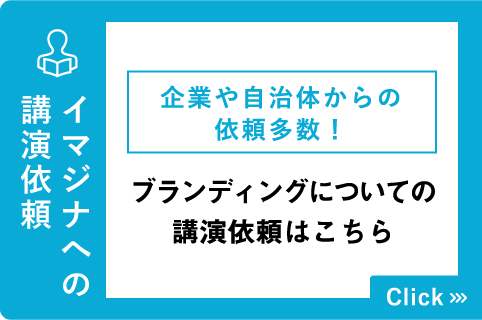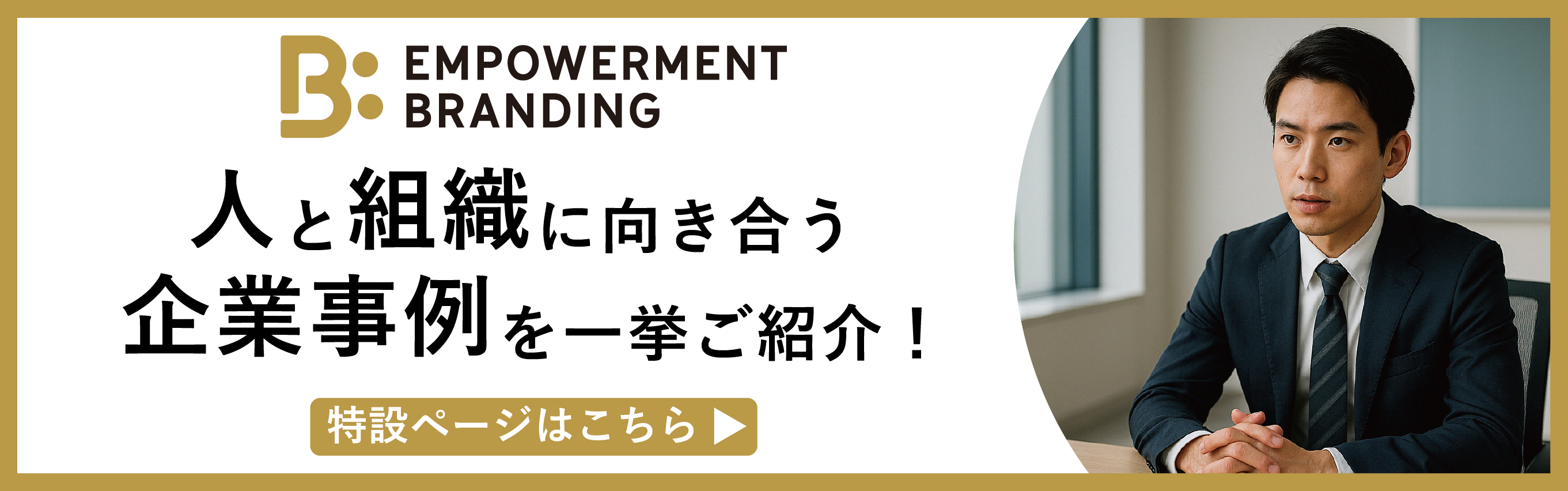一日のはじまり、まずはどの仕事から始めようか。そう考えてひとまずメールフォルダに目を通している、そんな方もいるのではないでしょうか。
毎日の食事や、行き先、さらにはキャリアプランなど、人生にはいろいろと悩むポイントがあります。
しかし、昼食のメニューを直感で決めるか30分かけて選ぶかでその後の人生の良し悪しが変わることはほとんどありません。それと同様に、あらゆる物事において、実は「選択にかける時間」というのはそれほど重要ではないと言われています。
「ファーストチェス理論」というものをご存知でしょうか。
チェスの名人が「5秒で考えた打ち手」と「30分考えた打ち手」とを比べると、86%は同じになる、という理論のことです。
この考え方はソフトバンクの孫正義氏も採用しており、彼は「どんなことでも10秒考えればわかる。10秒考えてもわからない問題は、それ以上考えても無駄だ」と述べています。
判断にかける時間によって結果が大きく違わないのであれば、判断はなるべく早くして、短縮された分の時間を目標達成のための行動にまわした方が、組織の生産性はぐっと高まるといえるでしょう。
マッキンゼーの調査でも、「意思決定に多くの時間を費やす組織」と「意思決定に費やす時間が比較的少ない組織」を比較した際、「意思決定にかけた時間が有意義であった」と答える割合はほとんど変わらないことがわかっています。

そもそも、どちらの組織においても、「意思決定に費やした時間のうち80%以上が有意義だった」と感じているのはほんの一握り。意思決定にかける時間そのものに価値があると感じられるケースはほとんどないに等しいといえます。
あるとすれば、決断を実際の行動へと落とし込んで成果につながったことで、「あのとき悩んだ時間はやっぱり有意義だった」と思えることくらいでしょう。
しかし、同じくマッキンゼーの調査によると、回答者の半数以上が勤務時間の30%以上を意思決定に使っているといいます。
人材不足も深刻化する今の時代、限られたリソースで最大限の成果を生み出すためには、意思決定にかける時間を短縮し、全員でいち早く実行のフェーズへと移っていくことが必要不可欠です。
そしてそのような組織へと変わっていくには、経営層自らが決断のスピードを上げていくことはもちろんのこと、それ以上に、経営層が決定したことを全社へと落とし込んでいく際のスピードを上げることが求められます。
そこで鍵となるのが、管理職の「代弁力」です。
経営層が下した決定の背景をしっかりと理解し、その情報をいかにわかりやすく社員へと伝えていけるか。それが社員の腹落ちやモチベーションを左右します。
決定の背景や、それを達成することが何につながるかが明確であれば、社員もただ頼まれたことをやるだけではなく、どうやって目標を達成するのかを現場レベルで一人ひとりが考案することだって不可能ではありません。
「上がこんなふうに決定したから、今期の目標はこれね」
「まずはこの仕事をこなして」
そのように伝えられて、求められた以上のことをやってくる人はいません。
むしろ、仕事の全体像が見えないがために、本質的な目的を見失ってだんだんと理解にズレが生じ、結果求められた通りのアウトプットですらなくなってしまうという可能性も十分考えられるしょう。
仕組み化やDXなども叫ばれる世の中ですが、損失を減らし生産性を高めるためにまず取り組むべきは、コミュニケーションのロスを減らすことに他なりません。
システムやツールでの解決を目指す前に、まずは組織の根本課題に今向き合ってみませんか?
全国で開催中の経営・ブランディングセミナーでは、多くの企業で起こっている上記のような組織課題や、それに対して経営層・管理職が持つべきマインドセットについてお伝えしています。