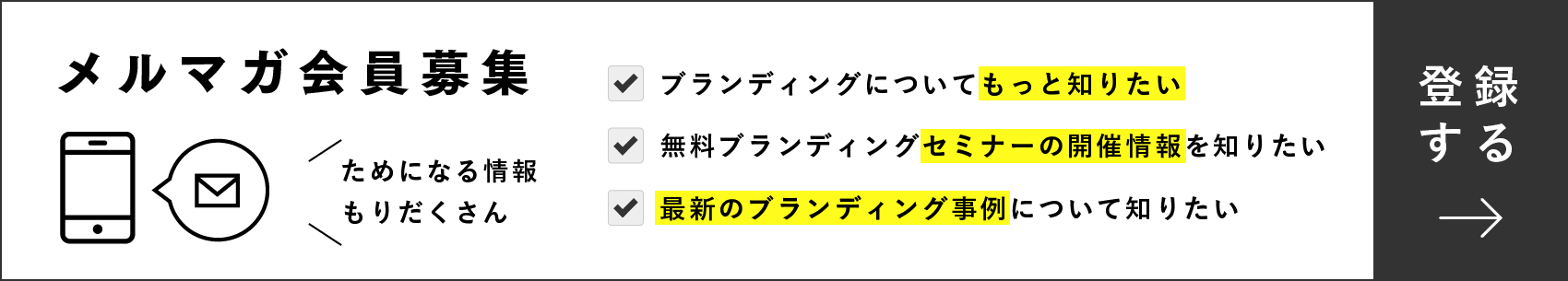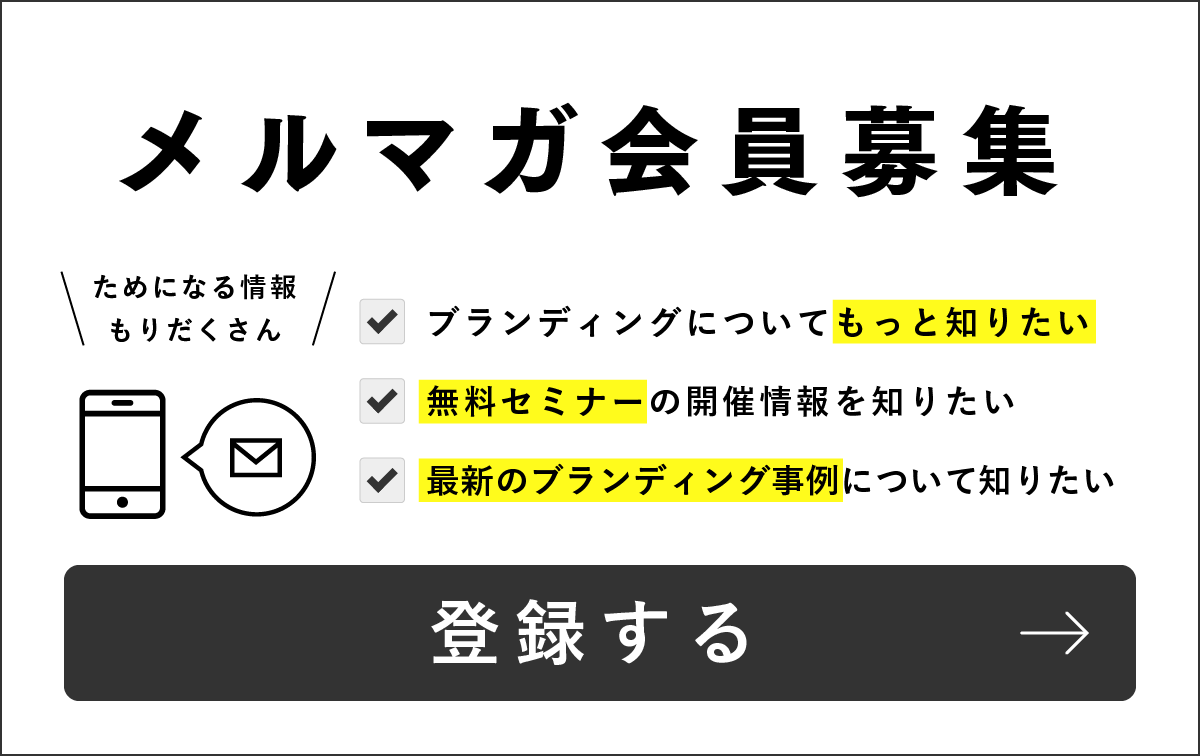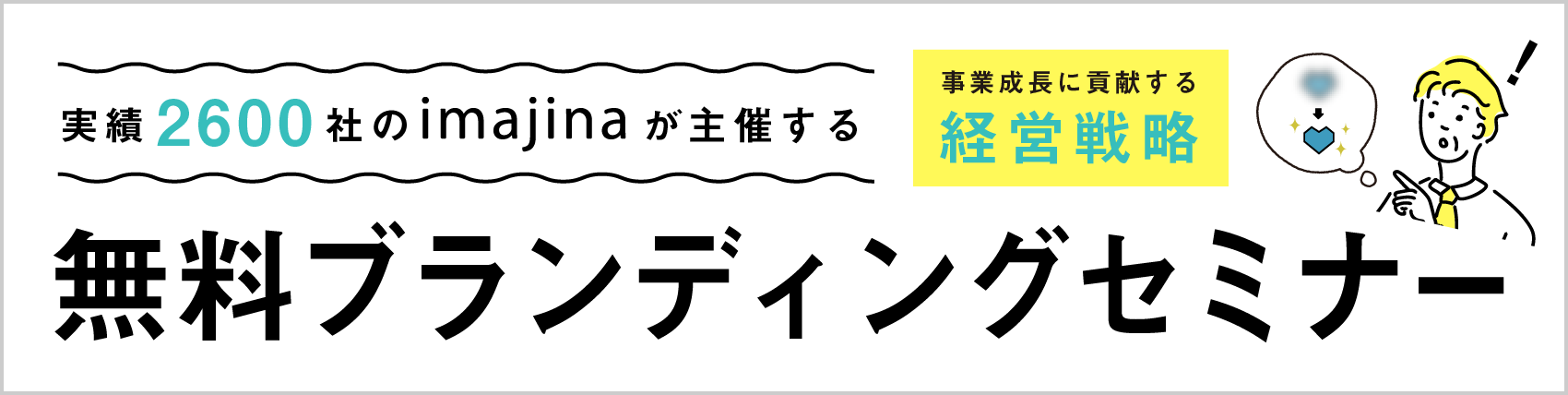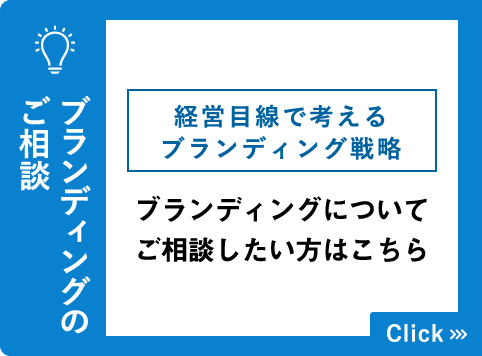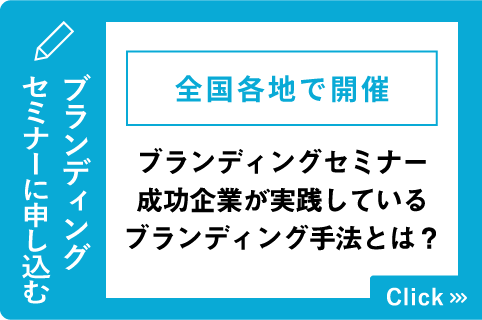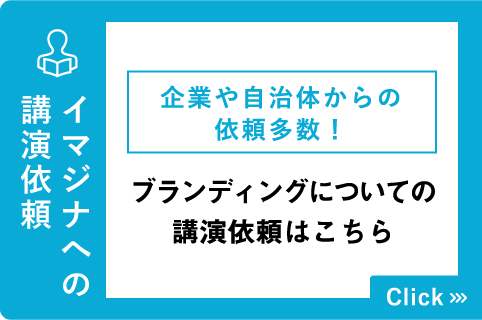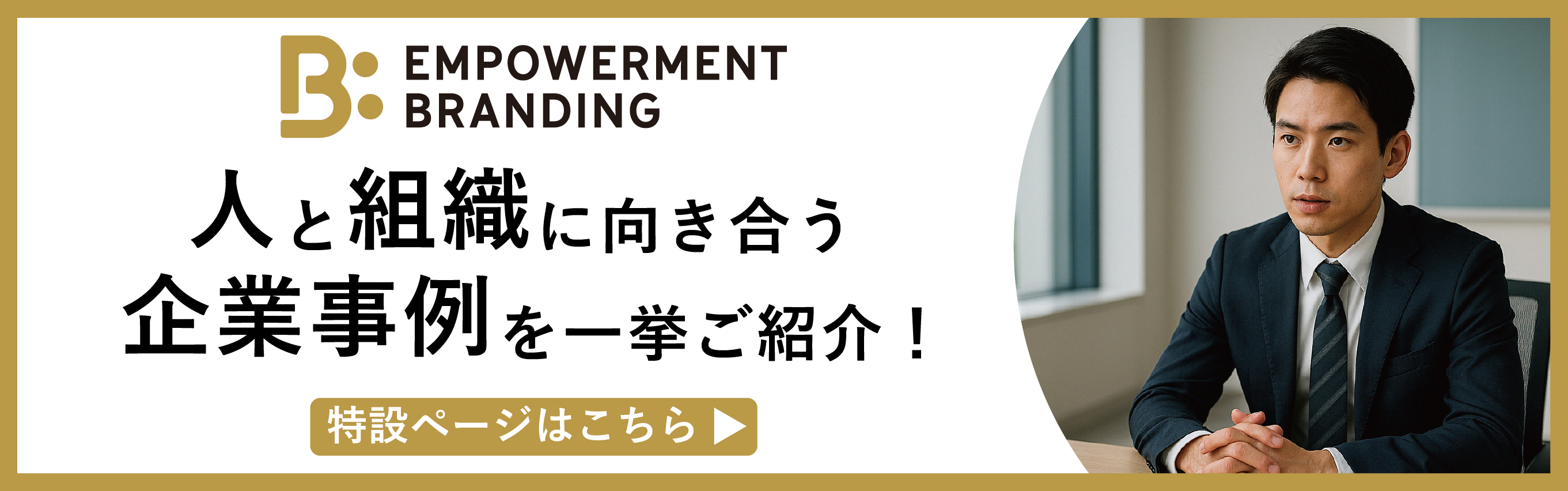「日本人は有言実行の意識が強すぎて、有言の幅が小さくなっている」
これは、アジア人女性初の宇宙飛行士・向井千秋さんの言葉です。
責任感の強い日本人は「やります」と言った次の瞬間には「達成する」というゴールに意識が全集中してしまい、有言実行の意志がかえって行動に踏み出す上での足枷となっている、といった意味での、この提言。
言ったからには絶対に達成しないといけないと思うあまり、現時点で達成できる見込みが大きい目標しか設定しなくなっているのではないかという主張のもと、向井さんは続けて、こう語ります。
「目標を達成するためのマイルストーンを設定することは必要ですが、それをどれだけ突き詰めてもビジョンにはなりません」
我々が考えなければならないのは目標そのものや、その達成可否ではなく、「どう達成に向かっていくか」というプロセスにおける「行動内容」なのではないでしょうか。
「何をあたりまえのことを」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今一度、立ち止まって考えてみていただきたいのです。現代の日本企業において、「決定」の段階で終わってしまう場合と、「実行」まで速やかに進む場合、果たしてどちらが多いのでしょうか。
日本企業では「決定すること」を「ゴール」としてしまう場面が少なくありません。
たとえば会議にて「可及的速やかにDXを推進する」という決定がなされたとして、いつまでに何をどのように進めるのかまで決めなければその「実行」に移ることはできないでしょう。
しかし、全員がその意見や案に賛成しており合意がとれているという状態を重視する日本では、まず「決定した」という段階で止まってしまい、決定事項を具体的に実行していくフェーズにはなかなか突入しないのが現状です。
何かを選択・決断することはスタートに過ぎず、その決断によって掲げた目標から逆算して、すぐにでも「どうやって実現するのか」を考えなければ進歩はありません。
実行のプロセスを突き詰めて考える意識が薄い日本人だからこそ、あまり行動の中身を追求しなくても手っ取り早くたどり着けそうな範囲でゴールを設定したり、「決定」の後にまったく動き出さなかったり、といった状況が生じています。
このような風潮を変えていくために我々は、常に頭に置いておかなければなりません。
物事の意味や価値は選択や決定そのものにあるのではなく、その後の実行によってのみ生まれるのだということを。
ジョン F.ケネディ米大統領は1960年代初め、演説にて「米国は10年以内に月へ行くことを決めた。容易だからではなく困難だからであり、我々の力や技能を結集させ、それがどれほどになるか示しうるからだ」と述べました。
そして実際1969年、フロリダ州から打ち上げられたアポロ11号で、人類は初めて月面に降り立ったのです。
やってみる前から、できる・できないの判断を悩むのではなく、目標を決め、達成するための行動を考え、実行の努力をする。
ここまで読んでくださったからには、今日から何かひとつでも「実行」に移せることを考えてから、画面を閉じてみませんか?